
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク

うちの子、IQ130だって!もしかして天才?



IQ85だった…。平均より低くて、がっかり…。
こんにちは、心理支援者の森山暖(もりやま はる)です。
知能検査や発達検査(WISC、田中ビネー、K式発達検査など)を受けられた保護者の方から、「うちの子はIQが高いので公立学校よりも私立に入れた方がいいですか?」「IQが低くてすごくがっかりしました。将来が不安です」といった、ご質問やご相談をよくお受けします。



IQだけを見て一喜一憂する必要はありません。IQはさまざまな要因により変動します。
検査の数値を正しく理解し、支援につなげましょう。
- IQに影響を与える4つの要因
- IQを正しく活用するための4つのステップ
この記事は各種心理的検査の倫理規定(秘密保持、適切な実施)を遵守し、公認心理師としての臨床経験に基づいた正しい知識と安心をお届けできるよう作成しています。
知能検査の基本的な知識については以下の記事も参考にしてください。
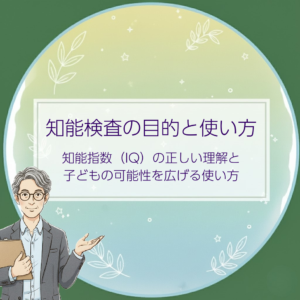
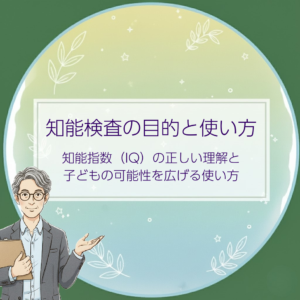


IQに影響を与える4つの要因



でも、IQが平均より下だから、頭が悪いってことなんでしょ?



実は、そうとも言い切れません。 数値はお子さんの「一面」にすぎず、 能力以外の要因でも変化することがあるんです。
IQを見る上で、気をつけたいポイントについて、いくつかの事例を元に解説します。
1. 検査による数値の違いと表す力
同じお子さんでも、異なる検査では数値が変わることがあります。
例:田中ビネーⅤとWISC-Ⅴを受けた太郎くん(8歳)
| 検査名 | 結果 | 検査の特徴 |
|---|---|---|
| 田中ビネーⅤ | IQ78 | 太郎くんの苦手分野である言語中心の課題が多い |
| WISC-Ⅴ | 全検査IQ88 (言語理解75、視空間110) | 得意・不得意の詳細な分析が可能 |
田中ビネーⅤのIQ78だけを見ると「境界域」と判断されがちですが、WISC-Ⅴでは視空間理解が110(平均の上)という優れた能力が明らかになりました。



なるほど、同じ知能検査でも測るものが同じではないんですね。
数値だけをみて誤った解釈をしてしまった例
実際の次郎くんの姿
- 機械の分解・組み立てが得意で、大人も驚くほどの技術力(視空間、処理速度の高さ)
- 実生活に必要な計算は問題なくできる(実用的知能)
- 好きな作業に集中して取り組める(集中力と持続力)
現在次郎くんは工業高校に進学し、将来は機械関係の仕事を目指しています。IQ72という数値からは想像できない、豊かな才能と可能性を秘めていたのです。


実際の美咲ちゃんの困りごと
- 完璧主義で、少しでも間違うとパニックになってしまう
- 友達関係がうまく築けず、一人でいることが多い
- 感覚過敏があり、音や光に敏感で集中が困難
- プレッシャーに弱く、期待されるほど萎縮してしまう
高いIQにも関わらず、美咲ちゃんは日常生活で多くの困難を抱えていました。「IQが高い = 何でもできる」は大きな誤解なのです。


IQが高いお子さんと保護者さんが陥りがちな危険については以下の記事も参考にしてください。


2.同じ数値でも背景が全く違う



同じ検査で同じ数値が出た場合でも、子どもの能力や背景が全く異なることがあります。
例:WISC-Ⅴの言語理解指標が同じ「85」の3人のお子さん
| Aさん(8歳) 言語理解85 | Bさん(8歳) 言語理解85 | Cさん(8歳) 言語理解85 |
|---|---|---|
| 語彙は豊富だが抽象的概念の理解が苦手 | 語彙自体が少なく基礎的な言葉の理解も困難 | 緊張すると実力発揮できないが、普段は流暢に話せる |
| 年齢相応の言葉を使うが、きちんと理解できていないことも多い | どんな場面でも言葉での表現が困難 | 集団では萎縮するが個別では年齢以上の語彙力 |
| 必要な支援:視覚的教材の活用 | 必要な支援:個別的な支援による基礎的な語彙力の積み上げ | 必要な支援:自信を持てる環境作り |
このように、同じ数値85でも背景や必要な支援が全く異なります。数値だけでは、どのような支援が効果的かは判断できません。
3.環境やコンディションによる数値の変動
同じお子さんでも、検査を受ける環境や心身のコンディションによって数値が変動することがあります。
例:花子ちゃん(9歳)の検査結果の変化
| 検査時期 | 環境・状況 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 初対面の検査者、病院の検査室 | 全検査IQ82 | 緊張が強く、疲れてもいた |
| 小学3年生 (2年後) | 慣れた検査者、学校の相談室 | 全検査IQ96 | リラックスして取り組めた |
同じお子さんでも、環境や心身の状態によって14ポイントもの差が生じました。



そうか! 検査は夕方だったから、疲れてたのかも…。 本当はもっとできるはず! 先生にもそう言わなきゃ!



ここも要注意です。「高い方が本当の力」と思いがちですが、支援の原則は逆。 あえて「調子が悪い時の結果」を基準にします。 お子さんが困るのは、まさに調子が悪い時だからです。
支援の原則をふまえて、花子ちゃんの支援方針は以下のようになりました。
花子ちゃんの支援方針
- 良いコンディション(IQ96)の時は、特別な支援がなくても力を発揮できる
- 悪いコンディション(IQ82)の時に困らないよう、この状態を想定した支援を準備する
- 緊張しやすい性格を考慮し、安心できる環境づくりや段階的な課題提示を行う
- 体調不良時でも理解しやすいよう、視覚的な手がかりやゆっくりとした説明を心がける
お子さんは毎日が最高のコンディションではありません。疲れている時、不安な時、体調が悪い時もあります。「調子が悪い時でも大丈夫」な支援があれば、お子さんは安心して様々な場面に取り組めます。
4. 発達は常に変化している
検査結果は「その時点での」能力を示すもので、お子さんの可能性を限定するものではありません。
例:健太くんの経年変化
| 年齢 | 全検査IQ | 変化の要因 |
|---|---|---|
| 6歳 | 78 | 言語発達の遅れが目立つ時期 |
| 8歳 | 89 | 適切な支援により言語理解が向上 |
| 10歳 | 102 | 自信がつき、全体的な能力が向上 |
健太くんは6歳時のIQ78から、10歳でIQ102まで向上しました。子供の力に合わせた適切な支援を受ければ、24ポイントの向上は決して珍しいことではありません。



なるほどね〜。これからの関わり方次第ってことですね。
まとめ:IQを正しく活用するための4つの手順
IQはお子さんの能力以外にも様々な要因で上下します。IQが出たら以下の手順で活用しましょう。
表面的な「IQ」の高い低いだけでなく、どの分野の力が得意で、どの分野で苦手かという「能力の凹凸」を正しく把握しましょう 。
時間帯や体調(眠気や疲れはなかったか)、緊張の度合い、音や光などの環境の刺激(集中できる環境だったか)等のコンディションを振り返り、お子さんの能力がどのような条件に左右されるのかを冷静に見極めます。
数値の背景を分析し、「どうすればこの子は力を出しやすいのか?」という条件を整理します 。
- 発揮できる場面の例:「視覚的な手がかりがある」「一対一の静かな環境」「いつもと同じ場所」など
- 発揮しにくい場面の例:「言葉だけの長い説明」「集団の中でのプレッシャー」「急かされる場面」など
この分析こそが、お子さんに合ったオーダーメイドの支援を考えるためのヒントになります。
分析した「力を発揮できる場面」を、家や学校の生活に取り入れます。同時に、「力を発揮しにくい場面」の時に、どのような支援があれば、無理なくこなせるかを考えます。
これにより、お子さんが「自分でもできる」「苦手な場面でも大丈夫」という体験を積み重ねることができます。
知能検査の結果にかかわらず、親として最も大切なのは、子どもの力を発揮できる場面を増やし、自己肯定感を育むことです。それが子どもの力を伸ばすことに直結します。
そのほか、以下によるある心配事をまとめました。
Q& A よくある質問
この記事は、実際の心理支援経験に基づいて作成していますが、お子さんの個別的な状況については、必ず専門機関にご相談ください。
【更新履歴】
2026年1月4日:画像を追加。参考事例を調整。
2025年12月20日:文章の構成を見直し、内容をよりわかりやすく修正。あわせて、記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
2025年10月16日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。
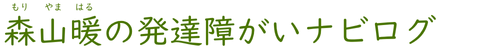
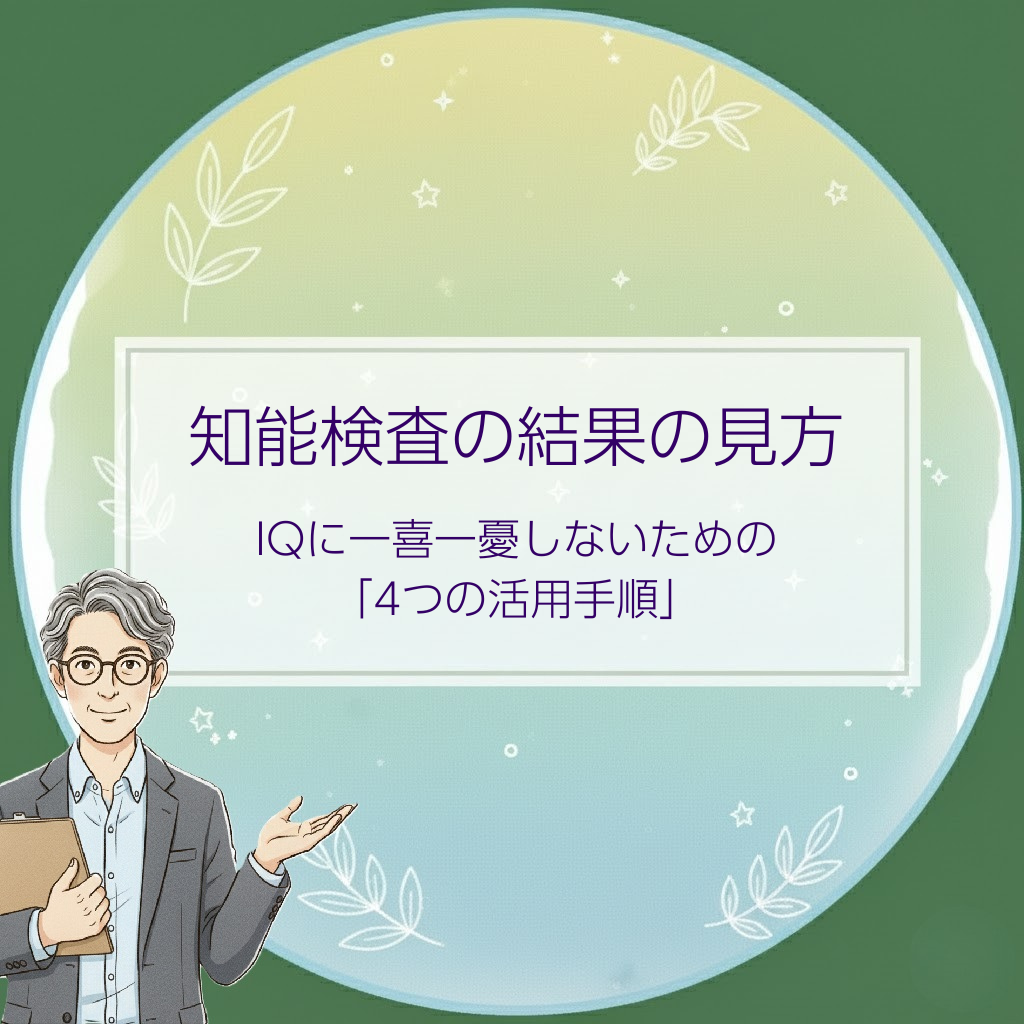

コメント