
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
【この連載について】
本記事は、「発達障害のあるお子さんのゲーム依存」について、公認心理師が専門的な知見から解説する連載の第2回です。第1回では、「WHO認定の診断基準と、発達障がいの子どもがハマりやすい科学的理由」を解説しています。👉 [第1回はこちら]
「うちの子はなぜこんなに夢中なの?😭」
第1回でお伝えしたように、発達障害のあるお子さんは定型発達の子どもと比べてゲーム障害になりやすいことが、多くの研究で分かっています。でも、それはお子さんの「我慢ができない」「意志が弱い」せいではありません。実は、お子さんの脳の特性と現代ゲームの仕組みが、「あまりにも相性が良すぎる」という、科学的な理由があるのです。
📚 【本記事で分かること】
今回は、ASDとADHDそれぞれの特性がなぜゲームと親和性が高いのか、そして特性を理解した上でのゲームとの付き合い方を具体的に解説します。
1. 🧠 ASD(自閉スペクトラム症)の特性とゲームの「危険な相性」
ASDのお子さんは、曖昧さを嫌い、明確なルールや論理的な仕組みを好みます 。ゲームは、現実のストレスを忘れさせる「完璧な安心空間」を提供してしまい、それが依存のきっかけとなります。
🔎 【特性1】曖昧さが苦手 ~「ルールが明確な世界」で現実逃避
現実世界はストレスに満ちていますが、ゲームは違います。
- ✅ 操作すれば必ず結果が出る
- ✅ ルールが明快で予測可能
この「明確さ」は、ASDのお子さんにとって非常に心地よい環境であり、依存が深まると、現実の不安から逃避する唯一の手段になってしまいます。
🏆 【特性2】強いこだわり・探究心 ~ゲーム内で完結する自己肯定感
ASDの特性である特定のテーマへの深い探究心は、ゲームの世界でこそ最大限に発揮されます 。
- 複雑な攻略法の発見、データ収集などが「上手さ」として認められ、低い自己肯定感を一時的に満たします 。
- しかし、この成功体験がゲーム内に限定されると、現実の活動への関心が完全に失われるリスクがあります 。
🫂 【特性3】現実の対人困難 ~ゲームは「安全すぎる居場所」
現実の対人ストレスや集団行動に困難を感じやすいお子さんにとって、ゲームは安心できる「安全基地」です 。
- ストレスが少ないソロプレイやテキスト中心の交流で充実感が得られます 。
- ゲームが「安全基地」だけになると、現実世界での挑戦や成長の機会を完全に奪ってしまいます。

2. 💥 ADHD(注意欠如・多動症)の特性とゲームの「爆発的な相性」
ADHDの特性である「今すぐの結果を求める反応」や「衝動性」は、ゲーム依存へのスピードを加速させる爆発的な要因となります。この背景には、脳の機能的な仕組みが大きく影響しています。
💡【公認心理師による解説】ドーパミンの罠とは?
ADHDのお子さんは、脳の特性上、「ドーパミン」(快感や達成感をもたらす物質)の働きが一般と異なります。現実世界での長期的な努力ではドーパミンが出にくい一方、ゲームはすぐに大量のドーパミンを与えてくれます。これにより、脳がゲームに強く惹きつけられてしまうのです。
🎁 【特性1】即時報酬への強い反応 ~「すぐ達成感」の罠
ADHDのお子さんは、「今すぐ得られる達成感」への反応が非常に強く、結果がすぐに出るゲームとの相性は抜群です 。
| 現実世界(時間がかかる) | ゲーム世界(即時報酬) | |
| 勉強 | 成果は数ヶ月後 | 数分でレベルアップ |
| 友達作り | 時間がかかる | すぐに仲間ができる |
この特性により、長期的な努力が必要なゲーム以外の現実の活動を「つまらない」「待てない」と感じてしまう危険性が高まります 。
🛑 【特性2】衝動性・行動制御の困難 ~親の介入を拒否
思いついたらすぐ行動してしまう衝動性は、ゲームの刺激性と合わさると、長時間・過度なプレイへと直結します ($2$)。
⚠️ 親御さんがやってしまいがちなNG行動
感情的にゲーム機を取り上げる、怒鳴るなどの衝動的な対応は、お子さんのパニックや暴力を誘発する引き金になりかねません 。お子さんの衝動性だけでなく、親の衝動性も制御することが求められます。
😵💫 【特性3】興味があることには止まらない!「危険な集中力」
興味のあるゲームには他の声が耳に入らないほどの過集中を発揮しますが 、その集中力のせいで、食事や睡眠といった生存に必要な行動まで疎かになることがあります。これは、単なる「集中」ではなく、依存性の高い「過集中」と捉えるべきです。(集中力の高さ=長所、とは限りません)
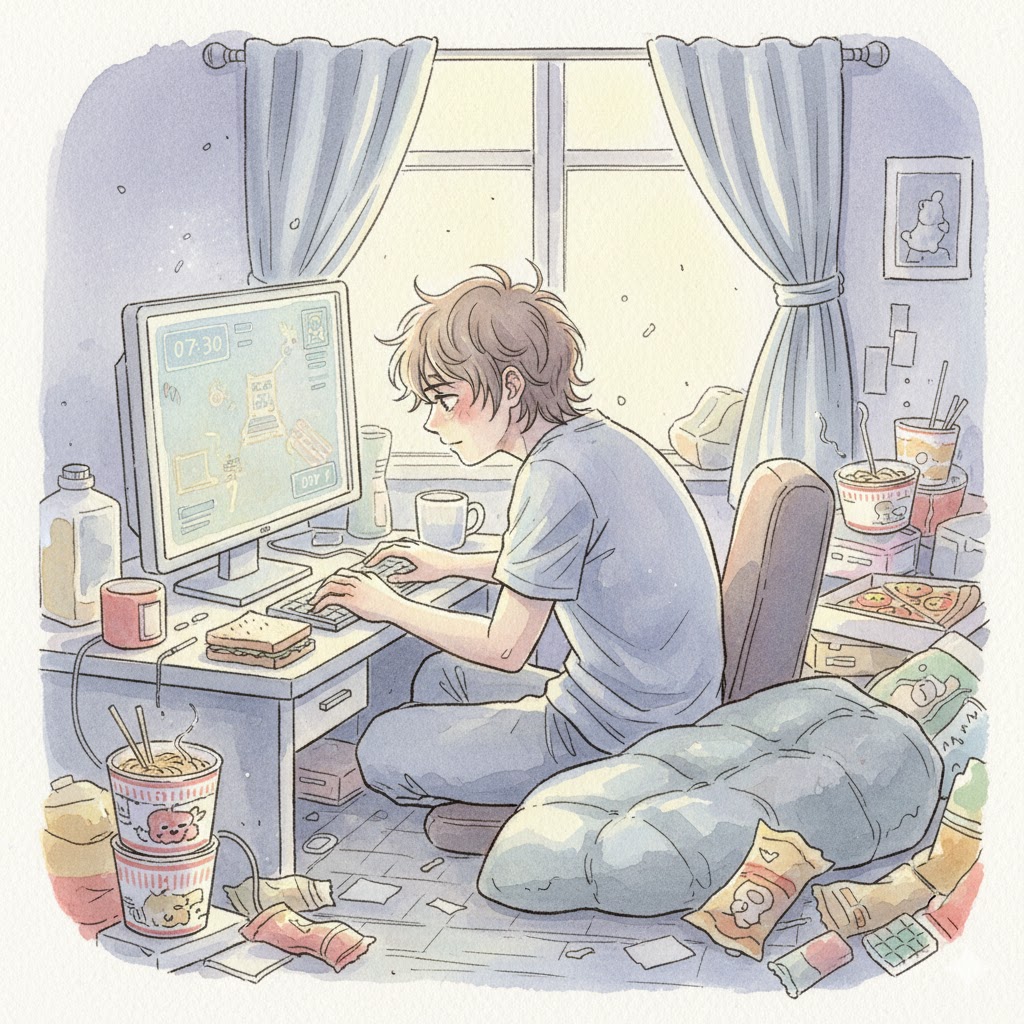
3. 🚨 見逃してはいけない!ゲーム依存の「危険なサイン」
ゲームは現実のストレスからの「避難場所」でもありますが 、以下のサインが出ている場合は、すでにゲームが生活を侵食し始めている警鐘です。
【受診・相談を急ぐべき重大サイン 5選】
- 生活の破綻: ゲームが最優先になり、昼夜逆転や睡眠不足が続いている。
- 暴力・暴言: ゲームを止めようとすると、暴力行為や激しい暴言・パニックを引き起こす 。
- 金銭問題: 親の財布からお金を盗む、または無許可で多額の課金をしている。
- 現実の放棄: 不登校や成績の急激な低下など、学業や現実の活動への重大な支障が出ている 。
- 時間の増加: ゲーム時間を減らそうと試みたが失敗し、かえって使用時間が増えている。
🤝 4. 【公認心理師からの提案】わが子を責めない段階的サポート法
ゲームとの向き合い方は、感情的な「完全禁止」ではなく、「共存しながら段階的に進めるアプローチ」が推奨されています 。改善はすぐには現れません。長期戦になることを覚悟し、「親子の信頼関係」を土台にして、焦らず進めましょう。✨
ゲームとの付き合い方を変える3つのステップ
- 【Step 1】関係性修復と情報収集:「なぜ?」を理解する
- 【Step 2】協働的ルール設定:「一緒に」決める
- 【Step 3】代替活動と自己肯定感:「現実の居場所」を作る
Step 1:関係性修復と情報収集:「なぜ?」を理解する
お子さんを「批判する」のではなく、「教えてほしい」と興味をもって傾聴しましょう 。お子さんがゲームに逃げ込んでいるのは、現実世界で何かしらのストレスを抱えているサインです。
- まずプレイ時間や課金履歴など、現状を把握します。
- 感情ではなく、事実に基づいて話し合い、親子の信頼を再構築することが最優先です。
Step 2:協働的ルール設定:「一緒に」決める
ルールを親が一方的に押し付けると反発を招きます。必ず、お子さんと合意しながら進める「協働的」な姿勢を大切にしましょう 。
- 守れそうな小さなルールを少数設定し、本人と合意を重視します 。
- ルールが守れたら、ご褒美でなくても「すぐに具体的に褒める」ことが大切です。
- 守れなかったら怒らず、理由を聞き、ハードルを下げて再設定しましょう。
Step 3:代替活動と自己肯定感:「現実の居場所」を作る
ゲームを減らすには、ゲームに代わる「楽しいこと」や「自信になること」が必要です。現実世界に、お子さんが「自分はできる!」と感じられる居場所を作りましょう。
- お子さんの興味に合ったゲーム以外の成功体験(習い事、家庭の役割など)を提供します 。
- お手伝いなど、家庭内の簡単な役割を与え、ゲーム外でも「自分は役に立っている」という実感(自己肯定感)を育てます。

5.🛠️ 発達特性を活かす!ゲームとの「お約束」を守る具体的な工夫(時間の見える化)
🎮 ゲーム時間管理のための構造化と「見える化」の活用
ゲームのルールが守れないのは、「時間や見通しを把握することの難しさ」という発達特性が原因のことが多くあります。まずは、生活のルールを整理整頓し、お子さんが「いつ、どこで、何をやるか」を明確に「見える化」する工夫が、支援の土台となります。
🧠 ADHD(注意欠如・多動症)のお子さんには
- 即時報酬と短い区切り:「ゲームをやめた後の行動」を明確にし、切り替えの難しさをサポート。
- 具体的な目標設定:「〇分ゲームをしたら、すぐに宿題に取り組む」など、次の行動を具体的かつ短い区切りで設定。
- モチベーション維持:守れたら即時報酬(例:ごほうぴポイント付与、「すぐ行動できてすごいね」等親からの肯定的な声かけ)を与えてやる気を維持。
- 時間の見える化:ゲームの残り時間を色や数字で示す「視覚タイマー」を必ず活用しましょう。
🧩 ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんには
- ルールの一貫性:ゲーム時間のルールは一度決めたら次の話し合いまで変えない(不確実性による不安を排除)。
- 視覚支援の徹底:「お約束」や「やめる手順」を文字、イラスト、チェックリストで明確に貼り出し「見える化」。
- 予告の視覚化:唐突な中断は混乱を招くため、「あと5分で終わり」など、予告を視覚的に提示し、次の行動へ安心して移行できるように導く。
💥 衝動的な行動・暴力への対応:冷静な対応と自己調整スキルの育成
ゲームを取り上げようとした際の感情の爆発や暴力・暴言は珍しくありません。親御さんが感情的に反応(例:大声で怒鳴る、ゲーム機を隠す)すると、事態は必ず悪化します。
この際は、無理に抑え込もうとせず、親が別の場所へ移動して距離を取るなど、安全を最優先にした回避策を検討しましょう。
💡 事前の「クールダウンの道具」準備
日頃から、ゲームから離れた落ち着いた状態の時に、「感情の交通整理」のスキルを一緒に練習しておきましょう。
- ゲームが中断されたり思い通りにならなかったりした時に、自分で気持ちを静めるための具体的な「クールダウンの道具」を教えます。 【具体例】「深呼吸を5回する」「好きなキャラクターの絵を描く」「お気に入りのクッションを抱きしめる」など。
- 衝動的な感情をコントロールする方法を身につけられるようサポートすることが重要です。怒りの感情を数値化する練習(例:怒りゲージで表現)」

🌈 最後に:ゲーム依存を防ぐ!親が今日からできる3つの行動
・「やめられないのは意思が弱いから」ではないと理解し、特性からアプローチする(責めない姿勢が最重要)
・感情的にならず、子どもと協働でルールを決める(一方的な禁止はNG)
・ゲーム外で「自分はできる」と感じられる成功体験(現実の居場所)を意図的に作る
お子さんがゲームに夢中になるのは、親の愛情不足や躾の問題ではありません。特性とゲームの相性という「科学的な理由」があるのです。 お子さんを責めず、医師や公認心理師などの専門家との継続的な連携を通じて、焦らず一歩ずつ、現実世界で輝けるよう支援していきましょう。
【参考・引用】
・厚生労働省「ゲーム障害の診断・治療法の確立に関する研究 総括研究報告書」2023
・日本精神神経学会「樋口進先生に『ゲーム行動症』を訊く」 https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=65
・厚生労働科学研究費 分担研究報告書「ゲーム障害の実態調査」2021
・国立病院機構久里浜医療センター「ゲーム依存相談対応マニュアル」2022
・厚生労働省「第2回ゲーム依存症対策関係者会議」2021
に悩む親へ:理解と対応の3ステップ-1-cleaned1.png)

に悩む親へ:理解と対応の3ステップ-cleaned1-300x300.png)

コメント