
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
子どもが「突然関係を切る」とき、実は何が起きているの?
SNSを消したり、突然友だちと連絡を取らなくなったり…。
「うちの子、何かあったのかな?」「また始まった」と心配や戸惑いを感じる親御さんが増えています。
最近耳にする「人間関係リセット症候群」とは、単なる気まぐれではなく、心が限界を迎えたサインかもしれません。
この記事では、公認心理師として子どものリセット行動の背景にある「見えないSOS」を解き明かし、保護者としてどのように安心感を提供できるかを具体的にお伝えします。
🧩 「人間関係リセット症候群」の正体は“心のSOS”
人間関係リセット症候群とは、これまでの人とのつながりをSNSの削除、連絡先のブロックなどにより、突然断ち切ってしまう行動のことです。
これは精神科の病名ではありません。むしろ、強いストレスや疲労を感じたときに、これ以上傷つかないために発動する「心の防衛反応」と理解してください。
「もう無理」「誰とも関わりたくない」という気持ちは、子どもが「これ以上頑張るエネルギーが残っていない」と心が限界を知らせているサインなのです。リセットは、彼らにとっての「緊急停止ボタン」なのです。
📊 現代の若者にリセット行動が増える理由
現代の若者世代では、このリセット行動が増加傾向にあります。令和7年に行われた全国調査では、「人間関係をリセットしたことがある」人が38%、さらに「今後リセットしたい」人が24%という結果が出ています[1]。
特に「友人・知人関係」でのリセットが多く、その背景には以下の要因が深く関わっています。
- つながりすぎる時代の息苦しさ:SNSによって「24時間365日」他者との関わりが可視化され、断る自由が奪われています。
- 見えない孤独の深化:内閣府の調査でも、全国の39.3%が『孤独を感じることがある』と回答しており、特に20〜30代では約50%に達します[2]。「SNSで繋がっているのに孤独を感じる」という現代特有の心理状態が、リセット行動の大きな要因になっています。
- 心の安定と人間関係のバランス: 厚生労働省の調査でも「人間関係が希薄なほど、こころの健康状態が悪化する傾向がある」と示されています[3]。リセットは、この「関わりたいが、疲れる」という相反する感情のバランスが崩れた状態と言えます。

🧠 発達特性のある子が「リセット」しやすい理由
発達特性(ASD・ADHDなど)を持つお子さんは、定型発達の子に比べ、人間関係でより大きなエネルギーを消費しやすいため、リセット行動につながりやすい傾向があります。
● ASD(自閉スペクトラム症)タイプの子の場合
- 曖昧さへの過剰な負担:場の空気や遠回しな表現、暗黙の了解を読み取るのが難しく、常に翻訳機をフル回転させている状態です。これが極度の疲労に繋がります。
- 完璧主義・全か無か思考: 「この関係はもううまくいかない」と感じた際、段階的に距離をとる“グレーな選択”ができず、「最初からやり直すしかない」という思考から、関係を完全に断ち切りやすい側面があります。
● ADHD(注意欠如・多動症)タイプの子の場合
- 衝動的な行動:感情の浮き沈みが激しく、強い怒りや悲しみを感じた時、「今すぐこの辛さを遮断したい」という衝動から、深く考えずにアカウント削除やブロックをしてしまいがちです。
- 見通しの立てづらさ: リセットした結果、その後の人間関係がどうなるかという見通しを立てるのが苦手なため、後で「やりすぎた」と後悔することも少なくありません。

🏡 保護者ができる3つの関わり方:リセット行動を「成長のステップ」に変える
子どものリセット行動に直面した時、親がすべきは「問い詰めること」ではなく、「安全基地」を提供すること**です。
① 「頑張ったサイン」として、まず受け止める
リセットは「もう限界だよ」という心の叫びです。まずは「今はすごく疲れてるんだね」「誰とも関わりたくないくらい辛かったんだね」と、子どもの感情をそのまま言葉にして受け止めてあげましょう。理由を問い詰めたり、「友達に失礼だ」と責めたりするよりも、心が落ち着くまでそっと休ませる時間が何より大切です。
② 家を“絶対的な安心基地”にする
外でどれだけ人間関係がうまくいかなくても、「家に帰れば、ありのままの自分でいられる」と思えること。これが子どもの心の回復力を最も高めます。話さなくてもいい、何をしても怒られない、という「無条件の受け入れ」の空気を作りましょう。「ここは、あなたにとって安全な場所だよ」というメッセージが、自己肯定感を育みます。
③ 「グレーな選択」というスキルを教える
リセット行動を繰り返す子には、「人間関係を完全に切る(黒)か、全力で維持する(白)か」の二択しかないと思っている場合があります。ここで、「少し距離をとる」「返事を数日後にする」「会わない期間を作る」といった“グレーな選択”を教えましょう。リセットしなくても済む、「距離を調節するスキル」を身につけることが、子どもの今後の対人関係を豊かにします。
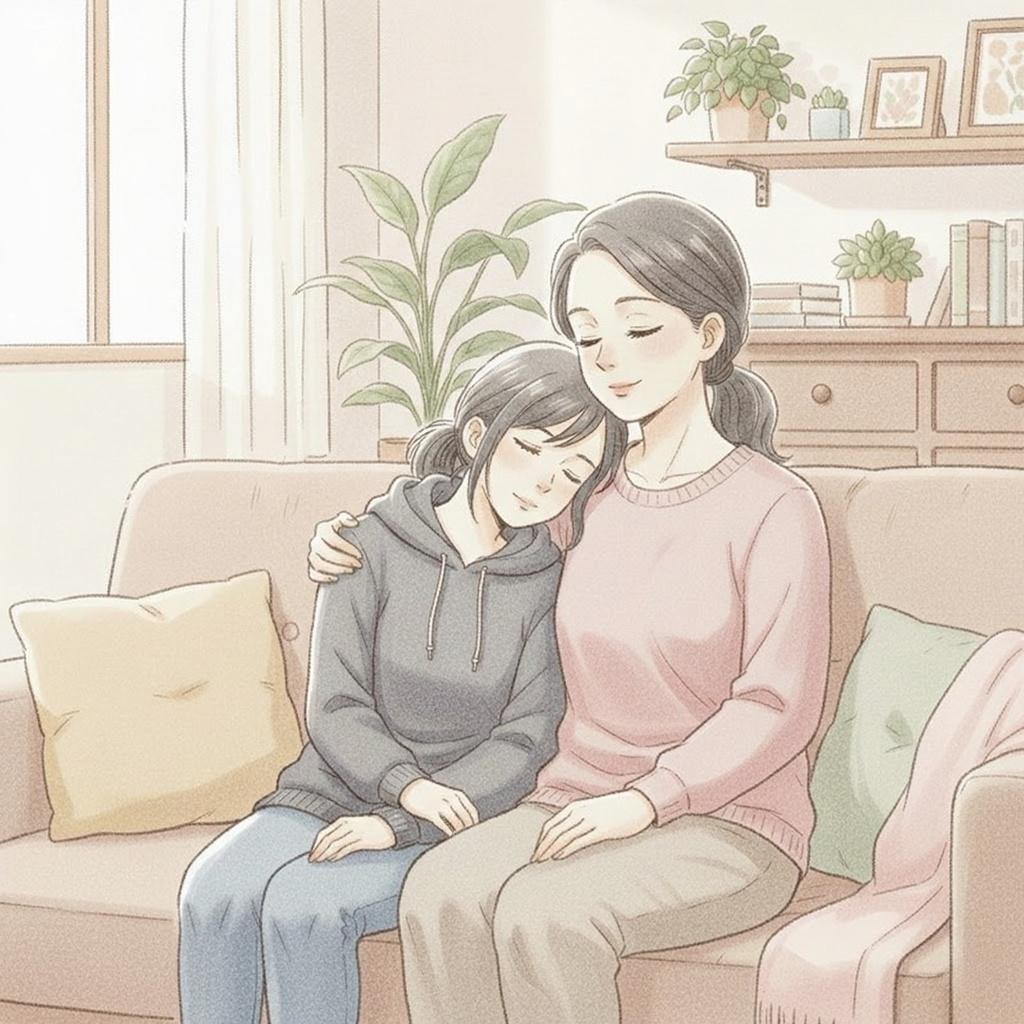
🌱 まとめ:リセットは「拒絶」ではなく「回復のための一時ストップ」
人間関係リセット症候群は、「人と関わるのが苦手な子」ではなく「真面目に、頑張りすぎた子」に起こりやすい心の現象です。子どもが人間関係を切り離すのは、誰かへの“拒絶”ではなく、“回復のための一時ストップ”だと捉えましょう。
保護者の皆さんが焦らず、ただ穏やかに見守り続けることで、子どもは家でエネルギーをチャージできます。「人とのちょうどいい距離」を見つけるという大切な成長の過程を、どうか温かい目で見守ってください。やがて、「もう一度つながってみよう」と思える日がきっとやってきます。
【参考文献】
- 株式会社クロス・マーケティング「人間関係に関する調査(2025年)」 https://www.cross-m.co.jp/report/20250115human
- 内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和6年)」
- 厚生労働省「厚生労働白書(令和5年度)」
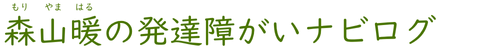






コメント