
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
「発達障がい」という言葉を聞くと、診断を受けることへの不安や、将来への迷いを抱える保護者は少なくありません。特に、「自分の育て方が悪かったのでは」「診断によってレッテルを貼られてしまうのでは」という自責の念や社会の無理解に、深く傷ついてしまう方もいます。
この記事では、公認心理師として23年間、発達障がい支援に携わってきた専門家の視点から、「診断を早く受けることが、なぜお子さんの未来を拓く戦略的な一歩となるのか」を明確にご説明します。発達特性は「治す」ものではなく、環境を調整し、お子さんが持つ力を最大限に引き出すための支援の「パスポート」です。保護者自身が、この特性を正しく理解し、迷いなく支援へと踏み出せるよう、具体的な情報とメッセージをお伝えします。
🚨「著者からお伝えしたいこと」
私は23年の経験の中で、「もう少し早く気づいていれば」と悔やむケースに数多く出会いました。家族が診断を恐れ支援が遅れたお子さんは、自己肯定感を失い、周囲の無理解な声に傷つけられ、本来持っていたはずの「伸びる可能性」を摘み取られてしまうのです。早く、正しく特性を知ることは、子どもを無理解な幼稚園や学校で傷つけられることから守り、その子の才能と個性を社会で活かすための最速の道です。診断は目的ではなく、お子さんの「生きづらさ」を解消するためのスタートラインだと捉え直してください。
1.発達障がいの基本的な定義
発達障がいとは、生まれつき脳の働きに特性があるため、主に社会生活や学習に何らかの困りごとがあらわれる状態を言います。この特性は、脳機能の多様性によるものであり、決して後天的な「親の育て方が悪かった」わけではありません。本人の努力不足でもなく、子ども自身や家族を責める必要はないことを、まず強調しておきたいと思います。発達の特性は、外部環境とのミスマッチによって「生きづらさ」を引き起こすのです。
日本では2005年に「発達障害者支援法」が施行され、発達障がいは以下のように定義されています。
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢で発現するもの」
このように、発達障がいは脳の特性によって生じる障害であり、症状は乳幼児期や学齢期にあらわれやすいことが特徴です。支援の本質は、「治すこと」ではなく、早期に特性を理解し、環境を調整すること(環境調整)にあります 。
2.発達障がいの主なタイプ
発達障がいは主に、自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)の3つに分類されます 。誰もがはっきりと分類されるわけではなく、それぞれの特性が重なり合っている場合が多いです。この複雑な特性を理解することが、適切な支援の第一歩となります。
1)自閉スペクトラム症(ASD)
社会性やコミュニケーション、想像力の面で困難さがみられる状態です。「スペクトラム(連続体)」とは、一人ひとりが異なる個性や特性を持っているということを表しています。
具体的な特徴としては、集団でのやりとりが苦手、自分の世界に没頭しがち、興味が限られる、変化を極端に嫌い、いつもと同じやり方や環境を好む(こだわり)、といった側面がみられます。
かつては「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」という名称が用いられていましたが、現在は知的発達の遅れの有無にかかわらず「自閉スペクトラム症(ASD)」という診断名に統一されています。

2)注意欠如・多動症(ADHD)
「注意が散りやすい(不注意)」「落ち着きがない(多動性)」「思いつきで動く(衝動性)」といった特性がみられます。忘れ物やうっかりミス、席を立ってしまう、順番を待つのが苦手など、年齢相応の行動と比べて著しい場合に診断されます。多動性が目立たなくても、注意の持続が難しい「不注意優勢型」と呼ばれるタイプもあり、大人になってから診断されるケースも増えています。

3)限局性学習症(SLD)
読む・書く・計算するといった特定の学習分野で、極端に困難を感じる状態です。知的発達に大きな遅れがないにもかかわらず、文字がうまく読めない、数字の理解が難しい、文章を書くことに大きな困難があるなどが特徴です。専門的なアセスメント(心理判定)を行うことで、具体的な困難の要因を特定していきます。

4)複数の特性を併せ持つ場合
発達障がいのタイプが一つだけでなく、複数重なるケースは少なくありません。たとえば、ASDとADHDを併せ持つ、SLDとADHDの両方の傾向があるケースも少なくありません。複数の特性が絡み合った、複雑な困りごとへの多角的な対応が支援の鍵となります。
3.年齢別の「気づきのサイン」と早期支援の目的
お子さんのいつもと違う行動や成長のペースは、家庭でも学校でも気になるポイントです。発達障がいのサインは年齢や発達段階によって異なります。サインを見逃さず、早期の環境調整につなげることが、お子さんの生きづらさを軽減し、将来的な二次障害(うつ、不安障害など)のリスクを予防する最も重要な予防措置となります 。
乳幼児期(0~5歳ごろ)のサイン
- 呼びかけても反応が薄い、目が合いにくい→(視線や他者への関心の欠如は、コミュニケーションの土台に関わる重要なサインです)
- 言葉の発達が遅い、一方的な言葉の繰り返しが多い→(言葉による相互的コミュニケーションの難しさを示唆します)
- 集団遊びや、ごっこ遊びが苦手
- 過度なこだわり(同じ道順を通りたがる、同じ物しか食べない)
- 並べる、回すなど同じ遊びを繰り返す→(限定された興味や反復行動は、ASDの特性として、特に注視すべき行動です)
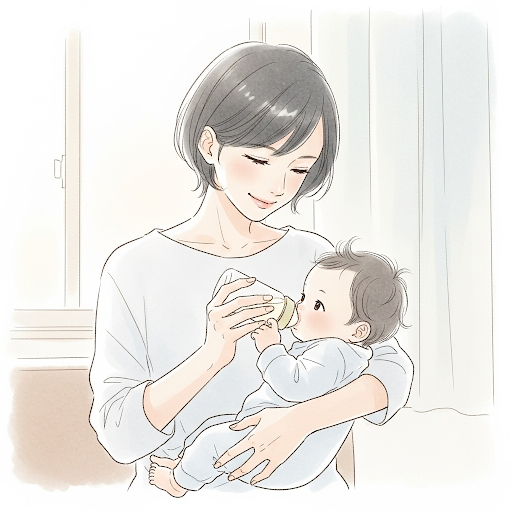
小学校低学年以降
- 授業中座っていられない、順番待ちができない→(多動・衝動性。席の配置や短時間の休憩導入などで軽減可能です)
- 忘れ物が多い、物をよくなくす→(実行機能障害(プランニング)の影響。忘れ物チェックリストなどの視覚支援が有効です)
- うっかりミスが多い
- 友達とのトラブルが多い、空気が読めないと言われる→(ソーシャルスキルの課題。具体的な場面を想定したSST(ソーシャルスキルトレーニング)が有効です)
- 読み書きや計算が極端に苦手→(SLDの可能性。専門的な個別指導法の導入が不可欠です)
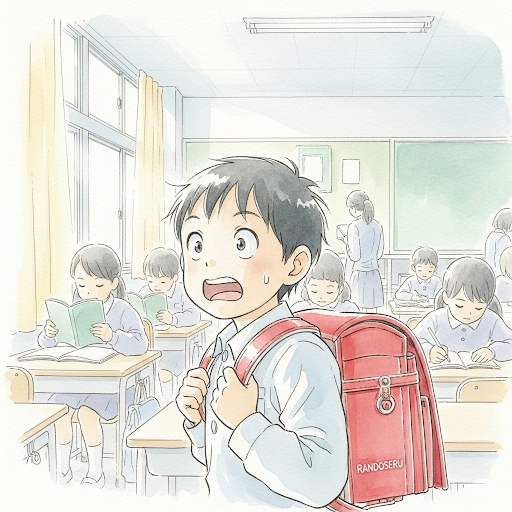
思春期・中高生
- 集団から孤立しやすい
- 強いストレスや不安による体調不良が増える→(二次障害の始まりのサインです。自己肯定感の低下が背景にあります)
- 学校に行けなくなる、引きこもる
- こだわりや気分の変動が強くなる
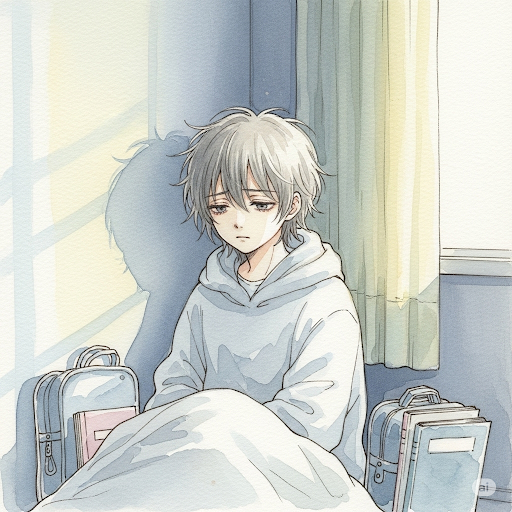
年齢とともにサインの現れ方は変わりますが、「保育園や学校でよく注意される」「家庭以外の場面で困りごとが目立つ」といった場合は、発達に何らかの特性が影響している可能性があります。思春期以降は、二次障害(うつ、不安障害など)のリスクが高まるため、特に早期の心理的サポートが不可欠です。特性を理解し、行動療法などで「生きづらさや困り感を改善」することが目的となります 。
4.いわゆる「グレーゾーン」について
診断基準を満たさないものの、集団生活や学習面で困りごとが生じている場合、「グレーゾーン」と呼ばれることがあります。この層は、診断名がないために周囲からの理解や支援が受けにくく、社会生活を送るうえで困難になりやすいことが指摘されています 。支援は診断名のみに依存するのではなく、困り感の度合いに応じて柔軟に行われるべきです。「うちの子は診断されていないから」と安心せず、気になる点があれば早めに専門機関に相談することが、将来的な生きづらさを予防するために大切です。
5.保護者が知っておくべき【3つの重要ポイント】
・早期発見・早期支援の大切さ:「二次障害」を防ぐ予防措置
発達障がいは早い段階で気づき、適切な支援を受けることで生きづらさが大きく軽減します。支援の本質は「治すこと」ではなく、「環境を調整し、本人の特性に合わせること」です 。特性を放置し、集団生活で失敗体験が積み重なると、不安障害やうつ病などの「二次障害」につながるリスクが高まります 。早期支援は、この二次障害の発生を未然に防ぎ、お子さんの自己肯定感を守るための、最も賢明な「予防措置」なのです。
例えば、騒音に敏感な生徒のために別教室を用意する 、抽象的な内容を絵カードや文字カードで視覚的に補完する 、といった環境調整は、特性に基づく困難を解消する具体的な「合理的配慮」であり、法的に保障された子どもの「教育を受ける権利」を確保するために行われます 。
・相談するタイミング:「診断」は不利益ではない、支援の権利パスポート
「診断を受けるのが怖い」「レッテルを貼られたくない」という保護者の気持ちは理解できます。しかし、私の23年の支援経験から言えるのは、診断は「不利益」ではなく、「支援を受けるための情報収集」であり、「支援を受ける権利を行使するためのパスポート」であるということです。相談が早ければ早いほど、その後の支援の選択肢が広がり、お子さんの進路(高校入試など)においても適切な合理的配慮(入試時間の延長、座席の変更など)を受けるための土台が築けます 。
「家では困っていないけれど、学校でよく指摘される」 「同年代より苦手なことが多い」 「担任の先生から相談された」などの場合、なるべく早めに地域の発達相談窓口や児童精神科、民間の心理相談機関などに相談しましょう。小さなことでも一人で悩まず、専門家に気軽に相談してください。
【著者の体験談:診断後の変化】
ADHDの特性を持つお子さん(小学校高学年)のケース。幼い頃から落ち着きがなく、母親は育てにくさを感じていましたが、「診断名がつくこと」を強く恐れ相談に踏み切れませんでした。しかし、学校でのいじめと不登校という二次障害が起こり、緊急で受診。診断後、「うちの子は怠けているわけではなかった」と特性を正しく理解し、専門家が介入したことで、母親は自責の念から解放されました。結果的に、学校側に座席位置の配慮(静かな環境の提供 )や視覚スケジュール の導入を求めることができ、半年後には笑顔で登校を再開しました。こういった事例は非常に多いのです。
診断はレッテルではなく、状況を改善するリソースを獲得する手段だと確信しています。
・家庭でできる工夫・配慮:環境調整と自己肯定感の育成
家庭でできる工夫は、大掛かりなことではなく、すべて「環境調整」の一環です。予定を絵や文字で見える形で示す(視覚スケジュール) 、必要なものを一緒にリストアップして忘れ物を防ぐ、といった小さな工夫が日常生活で役に立ちます。特に、肯定的な関わり(ポジティブな声かけ)は、自己肯定感を育み、思春期の二次障害のリスクを軽減する上で非常に重要です 。
支援の責任は保護者だけにあるわけではありません。国や自治体が法令や財政措置に基づき行う「基礎的環境整備」の上に、個別のニーズに応じた「合理的配慮」が提供されます 。保護者は、子どもの特性を最も理解する「支援計画の策定パートナー」として、自信を持って学校や専門家と連携してください。
【著者の体験談:「育て方」からの解放】
「夫や義両親から『母親の育て方が悪い』と責められている」というお母さんを多く見てきました。しかし、私たちが「発達障がいは脳機能の特性であり、母親の愛情や努力不足ではない」と専門的な知見を伝えると、お母さんは涙を流し、「救われた思い」とおっしゃいます。問題の本質は親の努力ではなく、子どもを取り巻く環境側にあります。保護者が自身を責めることなく、「私は子どもの特性を最も理解し、支援を実現させるパートナーだ」と自信を持つことが、何よりも重要です。
まとめ:お子さんの「個性」と「安心できる場所」
発達障がいの特性は、お子さんの個性や長所とも深く関係しています。たとえば、好きなものへの驚異的な集中力や独自の考え方は、その子自身の魅力や将来の可能性を育む力になります。
大切なのは、お子さんに合った環境や関わり方を工夫し、本人が「安心できる場所」を作ることです。ご家族や周囲が理解し、迷った時は専門家に相談することも、ぜひ大切にしてください。私たちが目指すのは、特性を隠すことではなく、特性を理解し、社会全体で支援の土台(基礎的環境整備)を築くことです 。
お子さんもご家族も「生きやすい毎日」になりますよう、今後も一緒に考えていきましょう。

この記事は、実際の心理支援経験に基づいて作成していますが、お子さんの個別的な状況については、必ず専門機関にご相談ください。
【参考文献】
- 「発達障害者支援法」2005
- 世界保健機関(WHO)「ICD-11」2023
【更新履歴】
2025年10月28日:参考文献を加筆。著者の体験談を入れて記事を再構成。あわせて記事タイトルを変更。
2025年10月10日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
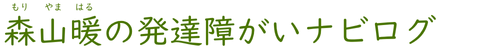







コメント