
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
お子さんの発達を支援する事業所選びは、単なる利便性の問題ではなく、お子さんの人生を左右しかねない決断です。なぜなら、発達障害のあるお子さんにとって、幼児期に受ける支援の質が、その後の学習面・生活面・二次障害のリスク——つまりお子さんの人生全体に大きな影響を与えるからです。
しかし現実は、厳しいものです。児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所数は急速に増加しましたが、支援の質にはきわめて大きな開きがあるのが実状です。多くの事業所は「預かり型」に偏り、本来の意味での「療育」をしていないところも少なくありません。
この記事では、公認心理師として23年間、2,000件を超える支援実績、そして里親経験を持つ筆者が、「本当の療育をしている事業所」と「預かり型にすぎない事業所」をどう見分けるかという視点で、お子さんの人生に役立つ療育先を探すためのポイントをお伝えします。
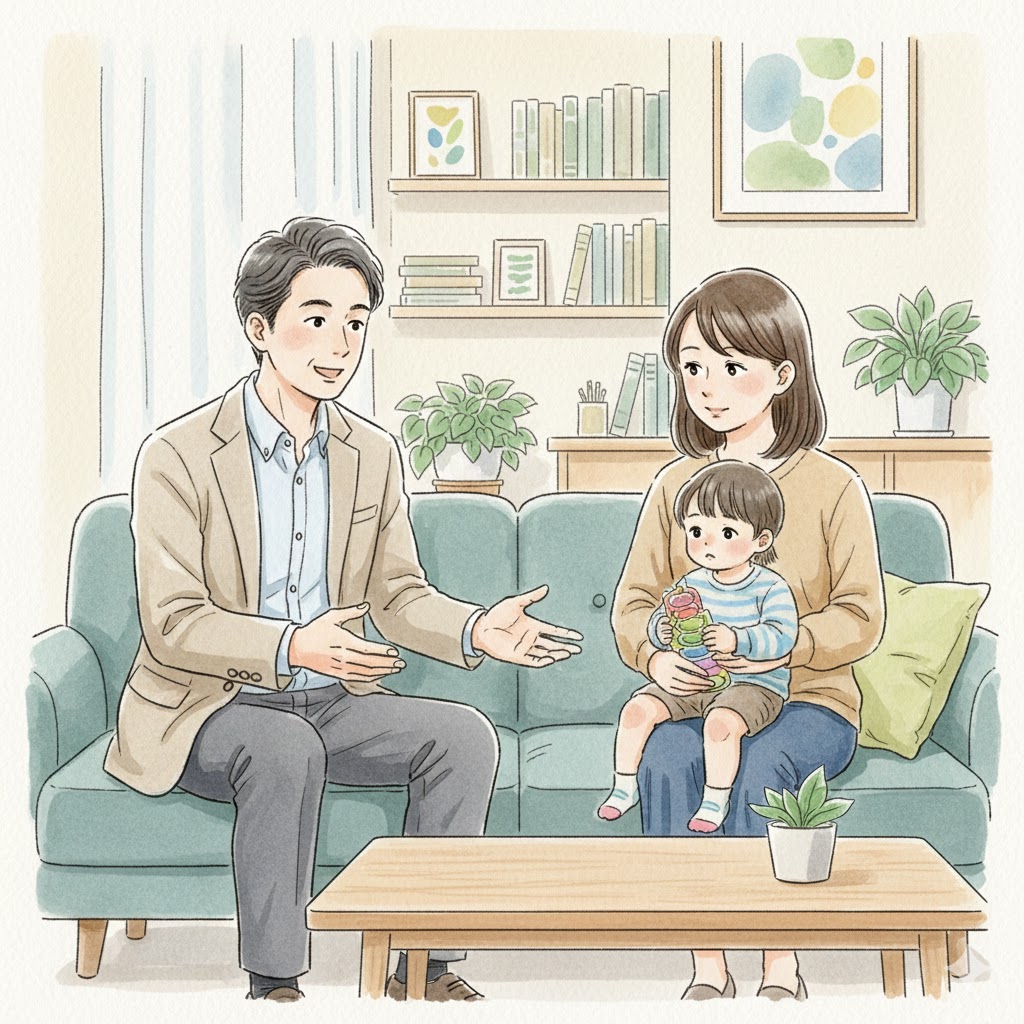
多くの療育先が「本当の療育」をしていない理由
事業所数の急増と質の低下
児童発達支援の事業所は、平成23年の約2,100カ所から令和3年には約9,000カ所へと急速に増加しました。その結果、市町村のガイドラインでも明記されているように、「提供される支援の内容が多種多様で、支援の質の観点からも大きな開きがある」という状況が生まれてしまったのです。
つまり、事業所の数が増えたのは良いことですが、質の確保が追いつかず、その結果として、形だけの「預かり」を行っている事業所が増えたという現実があるのです。
「預かり型」と「療育型」の違い
多くの保護者は、お子さんを預ける場所を探すことに目がいきがちです。そのため「送迎がある」「夜遅くまで預かってくれる」といった利便性を優先して事業所を選びます。事業所側も、こうしたニーズに応えることで経営を維持しようとします。
その結果、多くの事業所は預かり型へと傾いていくのです。毎日長時間子どもを預かり、その間に「何かプログラムをやっている」というスタイルでは、本当の意味での療育とは言えません。
一方、本当の療育を行っている事業所は、以下の特徴があります
- 限られた時間で、その子の特性に合わせた支援を集中的に実施
- 保護者との連携を最優先にしている
- 一日のプログラムが固定化されておらず、その日の子どもの状態に応じて調整
- 施設の見た目よりも、支援内容の実質性を重視
🚨 23年の経験から断言します:こんな事業所はすぐに避けてください
「預かり型」に傾倒し、支援の本質を見失った事業所では、お子さんの「最も貴重な時期」が無駄になってしまいます。利便性や安易な「預かり」を謳う事業所は、お子さんの発達にとってマイナスになりかねません。
これらの特徴がある事業所は要注意
- 預かり型であることを明確に打ち出している: 「長時間預かります」「送迎があるので安心」といった利便性を強調し、「何を支援するか」が不明確。
- 支援内容が不明確: パンフレットには「総合的支援」とあるが、実際のプログラム内容が見学時に説明されない。全児童に同じプログラムを提供している。
- 職員の専門性が明示されていない: スタッフの資格構成が不明確。「心理士がいます」と言うが、実際に子どもの支援に関わっているか不明。
- 保護者との連携が弱い: 送迎時の短いやり取りだけで、詳しい支援内容の説明がない。家庭での支援方法についてのアドバイスがない。
- 施設がスタイリッシュで、パンフレットが立派: 施設の見た目投資されている場合、それは「支援の質」への投資が疎かになっている可能性があります。例えば、オープンスペースや窓が大きい部屋は、見た目には魅力的ですが、聴覚過敏、視覚過敏を持つ発達障がいのお子さんにとっては、むしろ悪影響です。
- 早期教育・学習塾的なアプローチ: 「能力開発」「先取り学習」を謳っている。国のガイドラインが定義する療育は「各児童の障害の特性に応じた支援」であり、早期教育はむしろ有害になる可能性さえあります。
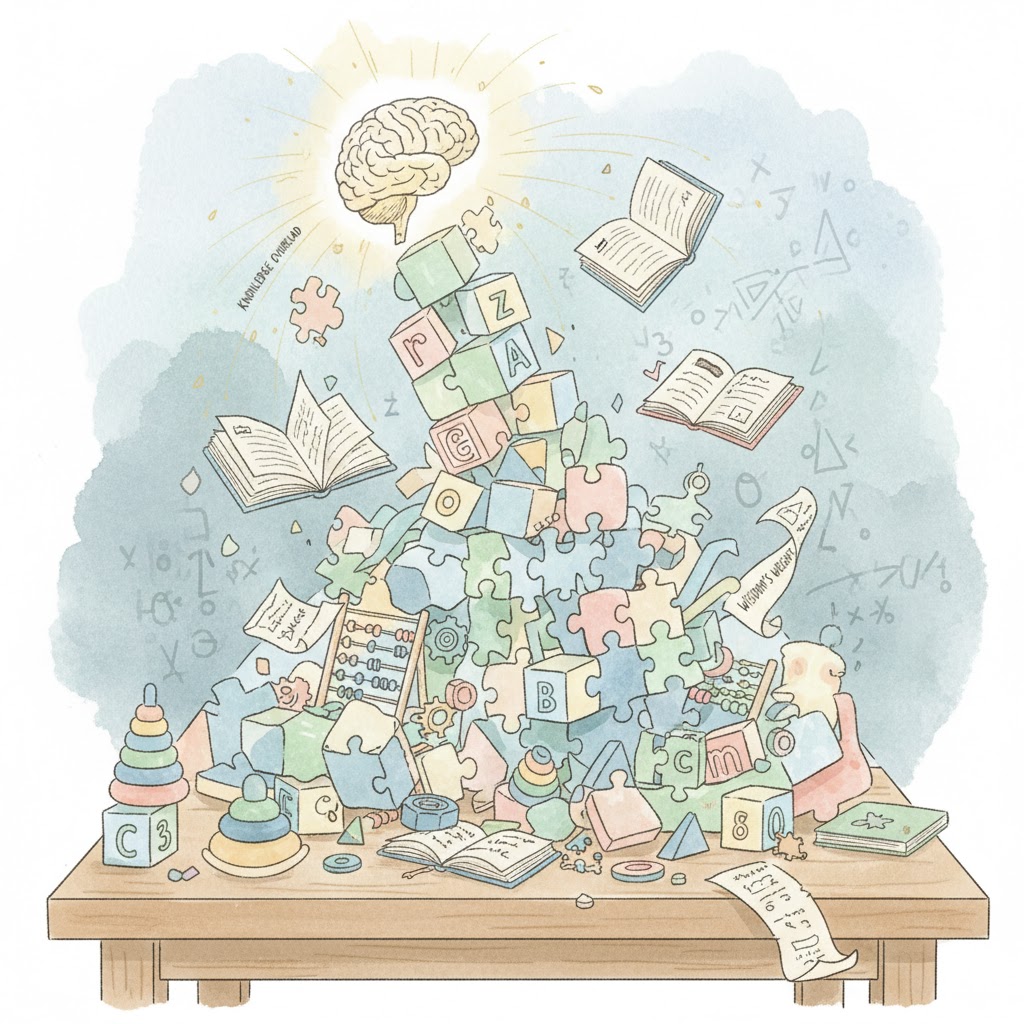
事業所見学時のチェックポイント
1. 支援方針とプログラム内容
- 事業所のコンセプトや支援に対する考え方が明確か
- 個別療育と集団療育のバランス
- 発達障がい療育にエビデンスのある支援プログラム(TEACCH、ABA、感覚統合など)
2. スタッフの専門性と人柄
- 保育士、児童指導員、作業療法士などの専門資格を持つ職員が常勤しているか
- 子どもへの接し方や雰囲気(指導員同士の連携は取れているか)
- 保護者対応の丁寧さ(面談の予約や説明は分かりやすいか)
3. 環境と設備
- 子どもの特性に配慮した構造化された空間(見通しが立ちやすいか)
- 安全で清潔な環境が整っているか
- 必要な設備や教材が充実しているか(子どもの年齢や発達段階に合っているか)
4. 保護者への配慮
- 支援中の様子を見学できるか(見学NGの場合は要注意)
- 定期的な面談やフィードバックの機会(個別支援計画の見直し頻度)
- 家庭での対応について具体的なアドバイスがあるか
5. 利用条件と実用性
- 利用可能な曜日・時間(他の予定と調整可能か)
- 土日や長期休みの際の受け入れ体制
- 他の利用者の年齢層や特性(お子さんに合う集団か)
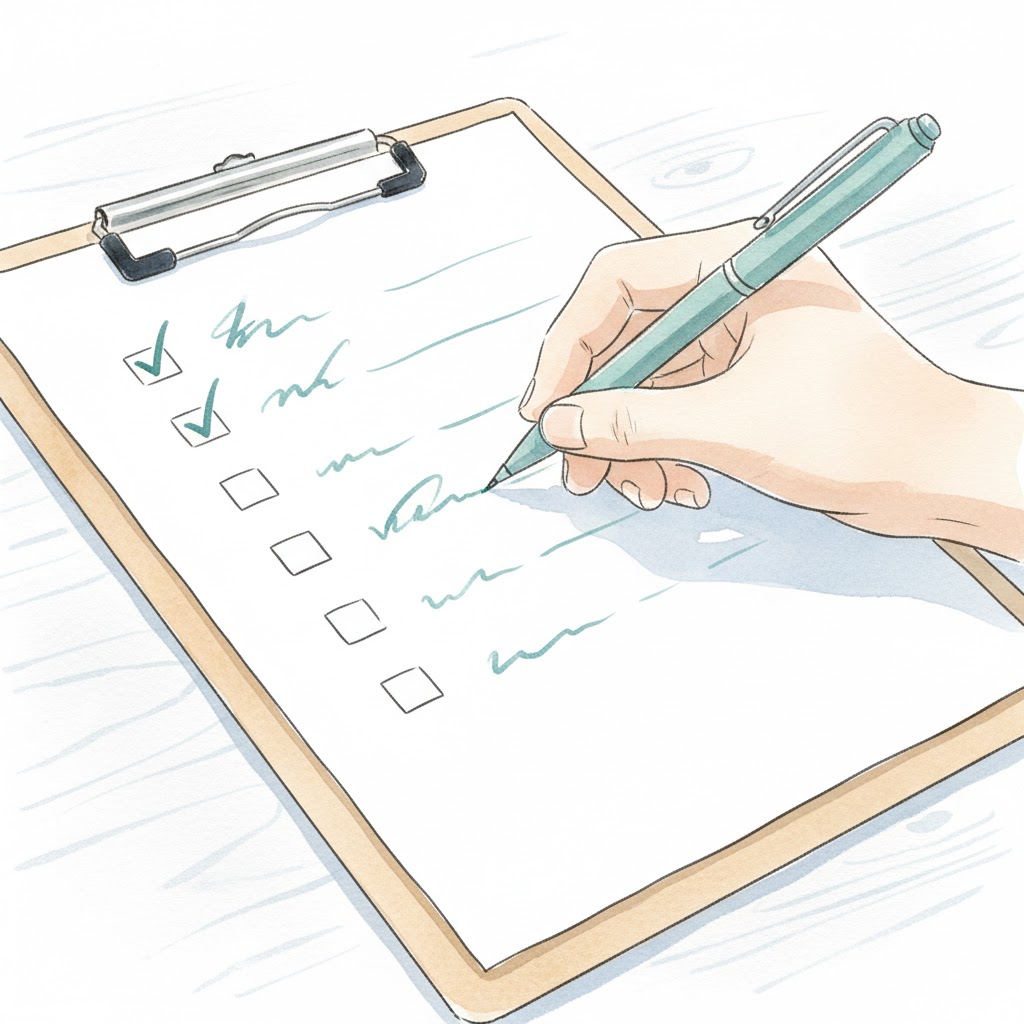
🚗 保護者送迎の「不便さ」は、実は「最大のメリット」です
「送迎がない事業所は不便」と考えるのは、実は大きな誤解です。質の高い療育を行っている事業所ほど、保護者による送迎を推奨します。それは、「療育は施設内だけで完結しない」という考えに基づいているからです。
【保護者送迎を選ぶべき3つの戦略的理由】
- 療育の様子を直接観察できる:実際にどのような支援が行われているか目で見て確認できます。支援者の子どもへの関わり方を確認できます。
- 支援者と密な連携ができる:その日の支援内容をくわしく聞くことができ、家庭での支援方法について具体的なアドバイスを受けられます。子どもの変化や課題について、支援者と直接やり取りできます。
- 子どもの気持ちが安定する:ご両親のお迎えで、お子さんは心理的に落ち着きます。療育への抵抗感が減り、帰宅後、親子関係が良好に保たれます。
両立の道:仕事の都合で送迎が必要な場合の「戦略的妥協点」
ただ、保護者の方々が仕事の都合から送迎付きの事業所を選ばざるを得ない現実も十分理解しています。しかし、利便性だけで支援の質を諦めてしまうのは避けたいところです。
もし送迎付きの「預かり型」事業所をメインで利用する場合でも、週に1日だけでも構いませんので、良質な個別支援を提供している事業所(送迎がないことが多い)を併用してください。良質な支援者が在籍する事業所での質の高い療育は、その短い時間であっても、お子さんの発達に深く、長期的な効果をもたらします。
「預かり」と「良質な療育」を切り分けて考えることが、多忙な保護者の方にとっての、お子さんの最善の利益を守るための現実的な戦略となります。

早期教育的アプローチを見極める——避けるべき危険信号
一部の事業所は、「療育」という言葉を使いながら、実態は「早期教育」に偏ったプログラムを提供していることがあります。これは、親が「うちの子は遅れていない」と安心したいという心理に付け込んでいるケースも少なくありません。
「早期教育」ではなく「療育」を見分ける言葉遣い
事業所のパンフレットや説明会で、以下のような言葉遣いが多い場合は、危険信号です。
危険な言葉(早期教育型に偏りがち)
- 「能力開発」「才能開発」
- 「知能を高める」「IQを上げる」
- 「先取り学習」「読み書き計算」
- 「親の満足度が高い」「親から感謝されている」
本当の療育の言葉遣い(お子さん中心)
- 「お子さんの認知スタイルに合わせた」
- 「その子の得意なことから始める」
- 「生活に必要な力を育てる」(着替え、食事、コミュニケーションなど)
- 「家族全体をサポートする」(ペアレント・プログラムなど)
厚生労働省のガイドラインでも、「児童発達支援における支援は、単に知識や技能を教える早期教育ではなく、生活や社会参加を円滑にするための支援である」と明確にされています。
本当の療育とは何か——公的資料が示す定義
児童発達支援ガイドラインが示す「療育」
厚生労働省が策定した「児童発達支援ガイドライン」では、児童発達支援(療育)を以下のように定義しています
「障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助」
ここで重要なのは、単に「子どもを預かる」ことではなく、「障害の特性に応じた多角的な援助を行い、子ども本人の適応力と生きる力を育てる」という点です。
本当の療育が行うべき5つの領域
本当の療育を行う事業所は、以下の5つの領域において、個々のお子さんのニーズに合わせた支援を実施しています
- 1. 健康・生活: 生活のリズムや生活習慣の形成、基本的生活スキルの獲得、環境の構造化による安心感の提供など。
- 2. 運動・感覚: 姿勢保持や動作の改善、感覚特性(感覚過敏や鈍麻)への対応、身体の移動能力の向上など。
- 3. 認知・行動: 認知の発達と行動習得、時間・空間・数等の概念形成、認知の偏りや行動障害への対応など。
- 4. 言語・コミュニケーション:言語形成と活用、指差し・身振り・サイン等、多様なコミュニケーション手段の活用など。
- 5. 人間関係・社会性:他者との関わり形成、自己理解と情動調整、集団への参加と仲間づくりなど。
全ての領域に平均的にプログラムを用意するのではなく、個々のお子さんに応じた選択と集中を行うのです。
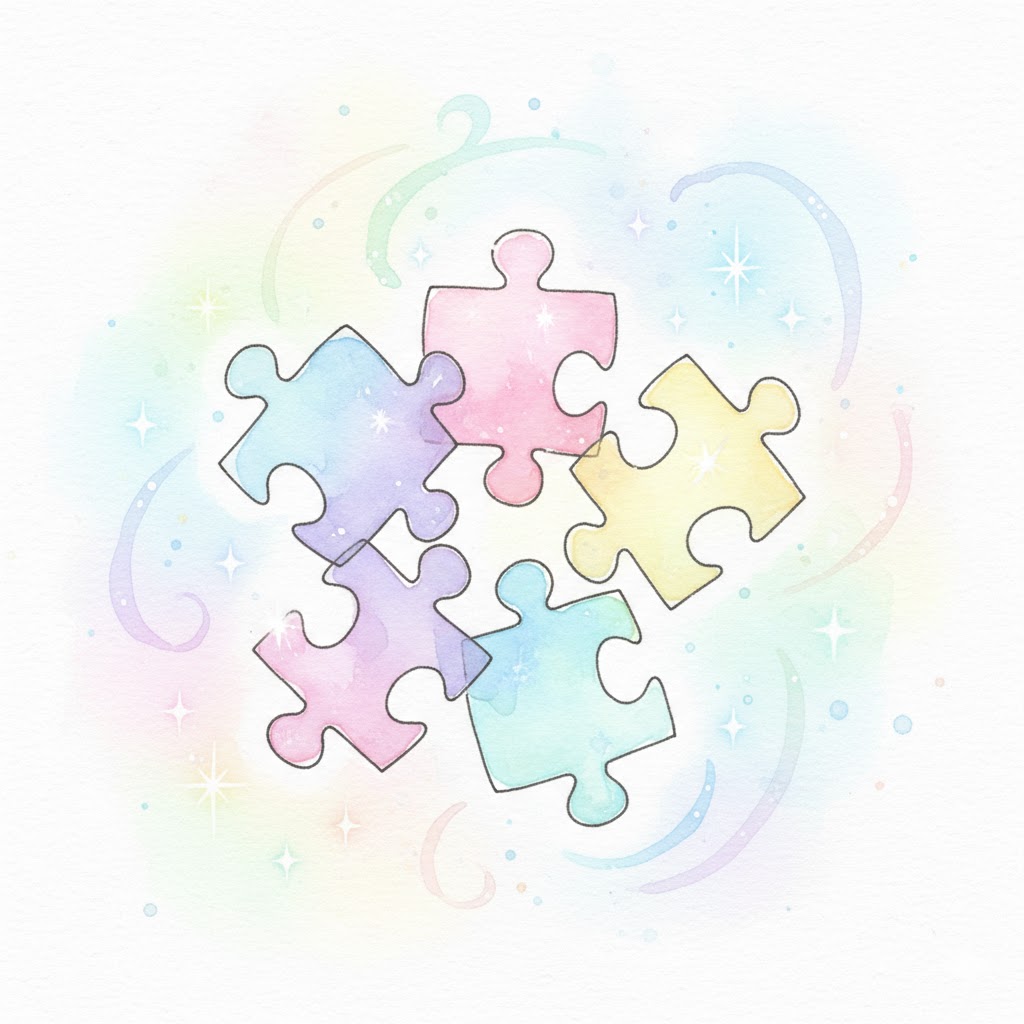
結論:「見かけだけの療育先」を避けることが、最も重要な選択
良い事業所を探すのではなく、悪い事業所を徹底的に避ける——これが最も現実的で、最も効果的な選択方法です。
お子さんの幼児期の数年間は、二度と戻ってきません。その時期に受ける支援の質が、お子さんの人生を左右します。
最終チェックポイントまとめ
避けるべき事業所
- 預かり時間の長さを強調する
- 支援内容が不明確な事業所
- 保護者連携が弱い
- 施設の見た目に力を入れている
- 早期教育的なアプローチ
検討する価値がある事業所
- 個別支援計画が詳細に作成されている
- 保護者との連携を最優先にしている
- 職員の研修体制が充実している
- 療育の定義と方法が明確に説明される
- エビデンスのある支援プログラム(TEACCH、ABA、感覚統合など)
お子さんの人生に直結する選択だからこそ、「利便性」よりも「実質性」、「見た目」よりも「中身」を優先してください。その選択が、お子さんの豊かな未来への第一歩になるのです。
【出典・参考資料】
厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」2024

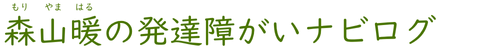






コメント