
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
「うちの子は学校で先生に褒められるから大丈夫」と、無理に言い聞かせていませんか。
中学生のお子さんについて、先生からの連絡帳には「授業態度も良く、友達とも問題なく過ごせています」と書かれている。けれど、その裏で、
- 家に帰るとリビングでぐったり倒れ込む
- 週末は一歩も部屋から出ない
- 家でだけ激しい癇癪や暴言で感情が爆発する
このような「外と内での二重生活」を送っているとしたら、それは危険なSOSのサインかもしれません。
お子さんは学校で「普通の子」を演じるために、命がけでエネルギーを消耗しているのです。心理学ではこれをカモフラージュ(マスキング)と呼びますが、その状態は二次障害のリスクが極めて高いことを意味します。
この記事では、公認心理師の視点から、この「見えない努力」の実態と、家庭で今すぐできる「子どもの心の充電法」をお伝えします。
【専門用語解説】カモフラージュ(マスキング)とは何?
カモフラージュとは、主に発達障害(特に自閉スペクトラム症:ASD)を持つ方が、社会的な困難や自分の特性を隠すために、意識的・無意識的に振る舞いを修正することを指します。
例えるなら、毎日、重い鎧(よろい)を着て過ごしている状態です。周囲に迷惑をかけないよう、必死で「普通」を演じているため、先生や友達からは「全く困っていない子」に見えてしまいます。
カモフラージュの3つの具体的な行動
お子さんが無意識に実践している努力は、以下の3つに分類されます。
- 真似(補償): 友達の話し方やジェスチャーをそっくり真似る、流行を調べて会話を練習するなど、技術で社会性を補う。
- 自己抑制(同化): 興味のないことに黙って耐える、感覚過敏でつらくても表情に出さないなど、「自分らしさ」をひたすら抑え込む。
- 仮面をかぶる(マスキング): 疲れや不安といった本音の感情を隠し、作り笑顔で乗り切る。

中高生の「電池切れ」が起きやすい3つの原因
なぜ思春期に入ると、このカモフラージュ疲れが限界に達しやすいのでしょうか?
1. 「空気読み」の難易度が急上昇
小学校ではシンプルな遊びが中心ですが、中学校以降では、グループ内での微妙な感情の読み合いや、暗黙のルールが重要になります。発達特性を持つお子さんにとって、この「空気読み」は脳をフル回転させる重労働です。
2. 「人と同じでいたい」願望の増大
思春期は、「みんなと同じでいたい」「浮きたくない」という気持ちが最も強くなる時期です。自分の特性を自覚し始め、「このままではいけない」という焦りから、さらに無理をしてカモフラージュを強化してしまいます。
3. 失敗を許さない「自分でやれ」の圧力
中学生になると、先生や社会から「自立」や「責任感」を求められる機会が増えます。しかし、特性上、タスク管理や段取りが苦手な場合、「ちゃんとできない自分」を責めることで、心がどんどん疲弊していきます。

絶対に見逃さないで!二次障害につながる危険なサイン
「普通に見える努力」を続けた結果、心が悲鳴を上げ、うつや不安障害、パニックなどの「二次障害」を引き起こすリスクがあります。これはお子さんからの「もう限界だよ!」という最後の訴えです。
保護者だけが気づける「危険なSOSサイン」チェックリスト
以下のサインは、学校では絶対に見えません。家庭での様子を振り返ってみてください。
| サインの内容 | 具体的症状 |
|---|---|
| 帰宅後の「屍(しかばね)状態」 | 家に帰るとすぐに横になり、声をかけても反応が薄い。食事すら億劫に見える。 |
| 感情のコントロール不能 | 外では大人しいのに、親に対してだけ激しく反抗、暴言、泣き叫ぶ(甘えているのではなく、疲れすぎている)。 |
| 身体の不調アピール | 毎朝「頭が痛い」「お腹が痛い」と訴える(特に月曜日や行事の前後)。 |
| 趣味や楽しみの放棄 | 以前熱中していたゲームやアニメ、スポーツに全く興味を示さなくなる。 |
| 極度の自己否定 | 「私はバカだ」「どうせ何もできない」といった強い自責の言葉を口にする。 |
もし複数当てはまる場合は、すぐに対応が必要です。専門機関への相談と並行して、後述の家庭でできる支援を始めてみましょう。

家庭を「安心できる充電基地」にする4つの方法
お子さんが学校で脱いだ「重い鎧」を安心して置ける場所、それが家庭の役割です。保護者の接し方を少し変えるだけで、お子さんの心は劇的に回復に向かいます。
1. 「家での姿=本当の姿」だと受け入れる
「なぜ学校でできていることが家ではできないの?」という考えを捨てましょう。「家でダラダラできる=学校でめちゃくちゃ頑張っている」の裏返しです。家での姿を「ワガママ」と捉えず、「エネルギーを使い果たした正直な姿」として受け止め、まずは「頑張ったね」と労いましょう。
2. 「義務のない時間」をたっぷり用意する
帰宅後は、勉強やお手伝い、翌日の準備など、「しなければならないこと」を強制しない時間を設けてください。特に特性上、静かな環境が必要な場合は、一人になれる「こもり場」を用意し、誰にも邪魔されない時間を保障することが最重要です。
3. 感情の「爆発」に共感の言葉を返す
お子さんが家で感情を爆発させたとき、「うるさい!」「いい加減にしなさい!」と怒鳴り返すのはNGです。「大変だったんだね」「つらかった気持ちを全部出していいよ」と、理由を問わずに感情を肯定してください。感情を受け止められると、「ここは安全だ」と心がリラックスし、冷静さを取り戻しやすくなります。
4. 「無理な矯正」をストップする
「もっと友達に合わせて」「挨拶くらいちゃんとしなさい」といった「社会に適応するための無理な矯正」を促すメッセージは、子どもの自己肯定感をさらに削ります。「あなたらしくていいんだよ」「失敗してもパパ/ママが守るよ」というメッセージを伝え続けることが、カモフラージュから解放されるための鍵です。
最後に:子どもの「見えない頑張り」を認めてあげてください
カモフラージュは、お子さんが「社会で生きていく」と決めて、毎日必死に続けている努力の証です。この目に見えない頑張りに気づき、理解しようとしている保護者の皆様こそが、お子さんの最大の理解者であり、最強のサポーターです。
「普通に見える」からこそ見落とされがちな苦しみに、この記事を通じて光を当てることができたなら幸いです。家庭という「心の充電基地」づくりは、決して完璧でなくて構いません。「無理しなくていいよ」というメッセージを親子で共有し、今日から一歩ずつ、お子さんの心が安らげる場所を一緒に作っていきましょう。必ず状況は変わります。応援しています。

【参考文献】
厚生労働省 「児童・思春期精神疾患の診療実態把握と連携推進のための研究報告書」2023
国立精神・神経医療研究センター「精神保健研究第50号:思春期・青年期における不登校・ひきこもりと発達障害」2021
兵庫県立特別支援教育センター「発達障害のある児童生徒のために ~二次障害の早期発見と予防~」2023
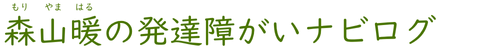






コメント