
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
第2回では、日常生活で特に困難を感じやすい、聴覚過敏と視覚過敏についてお伝えします。
「チャイムが鳴るたびに机の下に隠れてしまう」「蛍光灯の下にいると頭が痛くなって集中できない」……そんなお子さんをお持ちの保護者の方も多いのではないかと思います。
こういった行動は決して大げさな表現ではなく、お子さんは実際に耐えがたい刺激を感じています。
🎵 聴覚過敏:音への過敏性と対処法
見られやすい症状
音に過敏な人には、以下のような反応が見られることがあります
- 大きな音への強い反応
- 掃除機や花火の音で泣き出したり、パニックを起こす
- 運動会のピストル音や学校のチャイムが怖い
- 日常的な音への敏感さ
- 赤ちゃんの泣き声や子どもの騒ぐ声が耐えられない
- 蛍光灯の「ブーン」という音や時計の秒針の音が気になる
- 突発的な音への過敏さ
- 突然の音にビクッと驚く
- インターフォンや電話が苦手
- 騒がしい環境での困難さ
- 人混みや教室で人の話が耳に入らない
- 集中力が続かず、疲れやすくなる

具体的な対処法
1️⃣ 音環境の調整
家庭でできる工夫:
- 厚手のカーテンやカーペットで音を吸収
- 静音設計の家電製品を選ぶ
- 机や椅子の足にテニスボールやカバーを付ける
- インターフォンや電話の音量を下げる
2️⃣おすすめグッズ
| グッズ | 用途 |
|---|---|
| イヤーマフ | 全体的に聞こえる音を下げたい時 |
| ノイズキャンセリングイヤホン | 定常音(エアコンなど)を減らしたい時 |
| 耳栓 | 中程度の音を遮断したい時、外で使いたいとき |
| デジタル耳栓 | 必要な音は聞こえるが雑音をカット |
⚠️使用時の注意点
頻繁に使用すると過敏さが増す可能性があるため、必要な時と不要な時を分けて使用しましょう。

3️⃣ 事前の予告と心理的準備
効果的な伝え方の例
- ✅「これから掃除機をかけるね。3分くらいで終わるよ」
- ✅「運動会では10時頃にピストルが鳴るから、イヤーマフを準備しておこうね」
- ✅「疲れたら静かな場所で休憩しようね」
4️⃣学校・園での配慮のお願い
担当の先生に伝えたいポイント:
- 具体的にどんな音、どんな場面が苦手か。
- イヤーマフ等の使用許可
- 静かな場所での休憩の配慮
- 運動会等の行事の際の対応

👁️視覚過敏:光・色彩への過敏性と対処法
見られやすい症状
視覚過敏のあるお子さんには、以下のような反応が見られます
- 強い光への敏感さ
- 蛍光灯や太陽光がまぶしくて目が痛くなる
- 白い紙や画面を見ると頭が痛くなる
- 情報過多による疲労
- 人混みや視覚情報の多い場所で疲れやすい
- 点滅する光や強い光で気分が悪くなる
- デジタル機器への感度
- パソコンやスマホの画面を見るのがつらい
- ブルーライトによる頭痛や目の疲れ
具体的な対処法
1️⃣ 光環境の調整
家庭での工夫:
- 間接照明の使用で光の刺激を抑える
- 遮光カーテンで外光をコントロール
- 暖色系電球への変更
- デスクライトの位置調整で目に直接光が入らないようにする

2️⃣おすすめグッズ
| グッズ | 用途・特徴 |
|---|---|
| サングラス | 屋外での眩しさ対策 |
| 偏光グラス | 光の反射を重視した特殊メガネ |
| 遮光眼鏡(色付きレンズ) | 特定の色(波長)の光をカットし、眩しさやチラつきを軽減 |
| パソコン用メガネ | ブルーライトカット機能 |
| 色付き透明下敷 | 白い紙の眩しさ軽減 |
| つばの広い帽子 | 視界に入る光の制限 |
3️⃣デジタル機器の設定調整
すぐにできる設定変更:
- 画面の明るさを最小限に調整
- 文字サイズを大きくして読みやすく
- ダークモードの活用
- 15〜20分ごとの休憩を

家庭でできる環境づくりのコツ
安心できる「避難場所」の設置
感覚刺激が強すぎるときに、お子さんが落ち着ける場所を作りましょう
- 物理的な空間
- 段ボールハウスや小さなテント
- 分厚いブランケットで囲った空間
- 音と光を遮断できる部屋の一角
- 快適グッズの配置
- お気に入りのぬいぐるみや毛布
- 重みのあるブランケット
- 好きな音楽が聞ける音楽プレーヤー
予測可能性を高める工夫
- 苦手な感覚が予想される活動の前に予告する
- 「今日は○○するけど、疲れたら休憩しようね」と安心感を考える
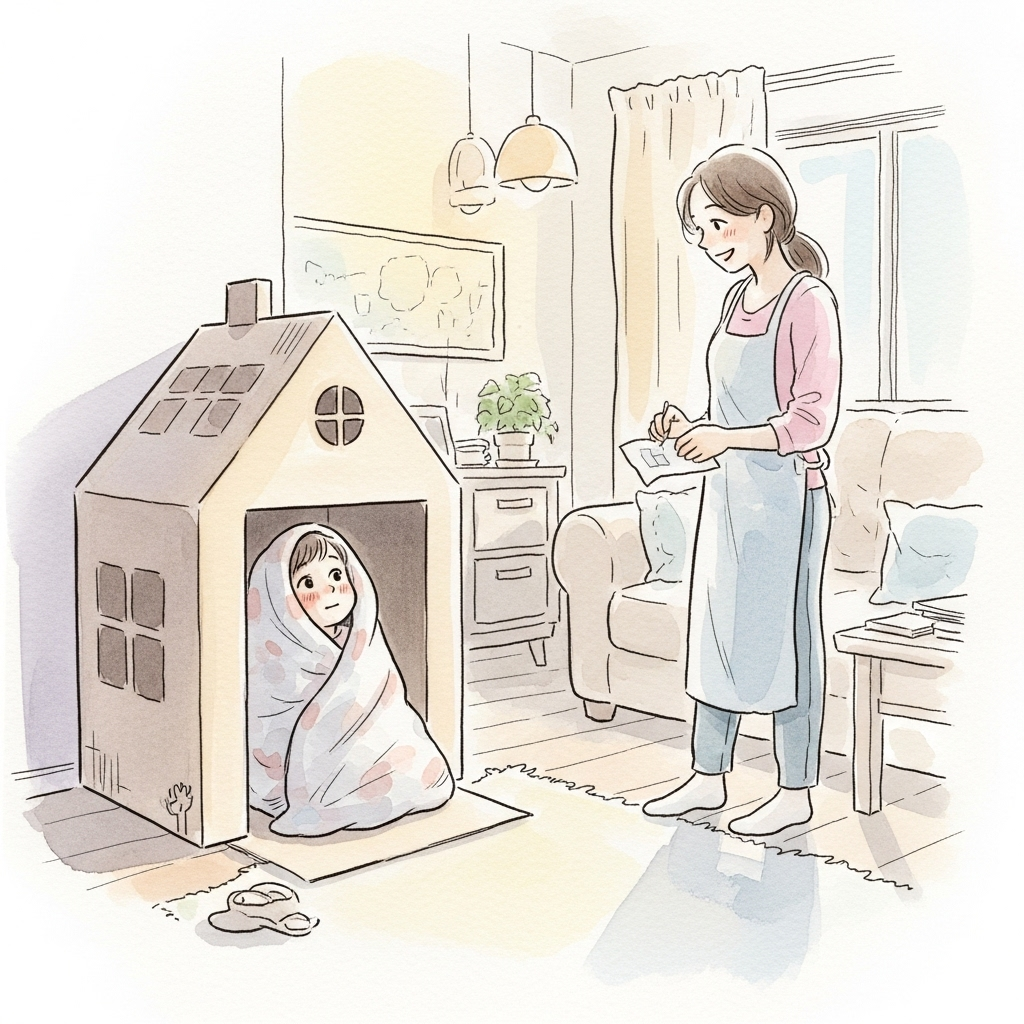
学校との連携
先生との情報共有のポイント
- 具体的に状況を伝える
- 「音に敏感」ではなく「チャイムの音で机の下に隠れる」
- 「光が苦手」ではなく「蛍光灯の下で頭痛を起こす」
- 対処法を一緒に考える
- 家庭で効果があった方法の共有
- 学校環境に合わせた対応方法の相談
- 緊急時の対応を相談する
- パニックになった時の対処法
- 落ち着ける場所の確保
配慮をお願いしたい具体例
- イヤーマフやサングラスの使用許可
- 座席位置の配慮(外の音が聞こえにくい席、スピーカーから離れた場所など)
- 集会や行事での事前説明と休憩場所の確保
💡専門家の力を借りる
先生への説明が難しい場合は、医療機関や相談機関の心理士・作業療法士に相談し、お子さんの特性と必要な配慮を記した文書(情報提供書)を作成してもらうことも有効です。専門的な視点からの情報が、学校での具体的な支援につながります。

保護者の皆さんへ
感覚過敏は一朝一夕に改善するものではありません。
- まずは理解から:「わがまま」ではなく「特性」として認識
- 環境調整を優先:無理に慣れさせようとせず、過ごしやすい環境づくりを
- 一人で悩まない:学校や専門機関との連携を積極的に
- 小さな成功を積み重ねる:できることから少しずつ、お子さんの自信を育む
感覚の敏感さはお子様の体調や疲労度によっても変化します。「今日はいつもより敏感かな?」と感じたら、無理をさせずに早めの休憩を心がけましょう。
次回予告
第3回は「触覚・嗅覚の過敏さとその対処法」について詳しくご紹介します。
- 服のタグがチクチクして着れない
- 柔軟剤や香水の匂いで体調不良になる
- 給食の匂いが苦手で食事ができない
このような困りごとへの具体的な対処法や、日常生活で使える工夫をお伝えします。
【更新履歴】
2025年10月12日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
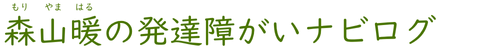







コメント