
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
第4回は、味覚過敏と温痛覚過敏について詳しく解説いたします。
「食べられる食品が制限されて栄養バランスが心配」「本気で入浴を嫌がる」「注射で普通以上の苦痛を感じる」といった悩みは、お子さんの健康や成長に直接関わる重要な問題です。
これらの過敏さも、これまでお話ししてきた他の感覚過敏と同様、強い不快感や苦痛としてお子さんが実際に体験しています。
👅 味覚過敏:味・食感への過敏性と対処法
💡 誤解しないで!
味覚過敏による偏食は、「わがまま」や「しつけ不足」とは全く異なります。お子さんは、特定の味や食感を「危険」または「激しい不快」として感じており、自力で克服することが非常に難しい特性です。周りの大人がまずそのつらさを理解することが大切です。
見られやすい反応
味覚過敏のあるお子さんには、以下のような反応が見られることがあります
- 味の強度への敏感さ
- 少量の塩味や酸味が非常に強く感じられる
- 苦味や辛味を過剰に嫌がる
- 甘味を「きつすぎる」と感じることがある
- 食感への強いこだわり
- 特定の食感(硬い、柔らかい、ざらざら等)を拒否する
- 複数の食材が混ざった料理を嫌がる
- 温度による食感の変化も苦手
- 栄養面での心配
- 食べられる食品が限られ、栄養バランスが偏る
- 給食を食べられず、昼食をほとんど摂らない
- 成長に必要な栄養素が不足する可能性
- 社会生活での困難
- 外食や友達との食事ができない
- 学校行事や宿泊学習で食事に困る
- 食事を巡って家族間でストレスが生じる
- 食指導などで「残さず食べる」ことを強いられることが大きな心理的負担となり、登校への不安につながることがある
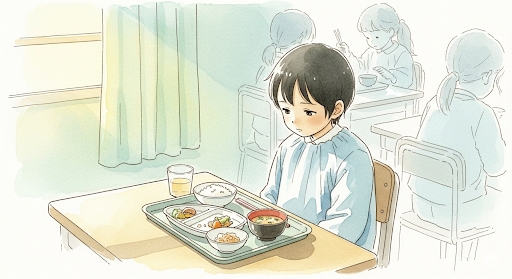
具体的な対処法
1️⃣ 食材・調理法の工夫
食感を調整する方法:
- 硬い食材は細かく刻んで好きな食べ物に混ぜる
- 調理法を変えて食感を調整する(揚げる、煮る、焼くなど)
- ミキサーやフードプロセッサーで細かくする
- 冷凍・解凍を利用して食感を変える
味付けの工夫:
- 薄味から始めて段階的に慣らす
- 調味料を少量加えて食べやすい味にする
- 温度調整で味の感じ方をコントロール
- 食材を分けて提供する

2️⃣段階的なアプローチ
スモールステップで少量から挑戦
| ステップ | 具体的な方法 |
|---|---|
| ①観察期間 | スプーンにすくうだけ、匂いを嗅ぐだけ |
| ②接触期 | 唇に触れるだけ、舌先で少し舐める |
| ③少量期 | 米粒大の量から始める |
| ④拡張期 | 慣れた食材から似たものへ応用 |
重要なポイント:
- ✅一口食べられたらその場ですぐに褒める
- ✅無理なく、子どものペースに合わせて
- ✅体調の良い時を狙って挑戦する
- ✅好きな食べ物と一緒に提供する
3️⃣ 食事環境の整備
リラックスできる食事環境
- 静かで落ち着いた雰囲気で食事する
- 家族が美味しそうに食べる様子を見せる
- 子どもと一緒に野菜を育てたり料理をする
- 食べやすい温度(冷たい、温かい)を意識する
- 食事中のテレビは控えめにして食事に集中する
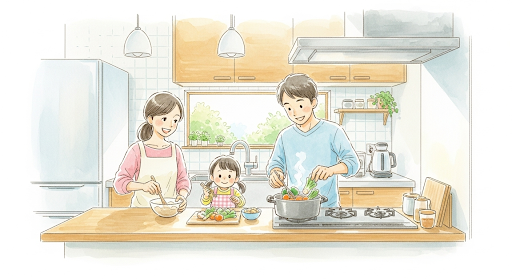
4️⃣ 便利グッズと栄養補助
調理器具
| グッズ | 特徴 |
|---|---|
| フードプロセッサー・ブレンダー | 食感を変える |
| すり鉢・すりこぎ | 少量の食材を細かくする |
| 製氷皿・シリコンカップ | 小分けして少量ずつ提供 |
| 分割プレート | 食材が混ざることを防ぐ |
栄養補助用品
| グッズ | 特徴 |
|---|---|
| ゼリータイプの栄養補助食品 | 学校や宿泊学習での栄養確保 |
| ブロックタイプの栄養食品 | 手軽に栄養摂取が可能 |
| 偏食用サプリメント | 不足しがちな栄養素を補う |
| 栄養強化された飲み物 | 乳飲料や野菜ジュース等で栄養補給 |
💡 栄養バランスは「1日」ではなく「1週間」で考える
毎日の栄養バランスを完璧にするのは非常に困難です。「この1週間で必要な栄養素が摂れているか」という長期的な視点に切り替えることで、保護者の負担が大きく軽減されます。必要な場合は、栄養補助食品やサプリメントを積極的に活用しましょう。
🌡️ 温痛覚過敏:温度・痛みへの過敏性と対処法
見られやすい反応
温痛覚過敏のあるお子さんには、以下のような反応が見られることがあります
温度感覚
- 気温変化への極度の敏感さ
- 過剰な暑がり・寒がりを示す
- 適切な衣服調節ができず、季節に合わない服装をする
- エアコンの設定温度で家族と意見が合わない
- 入浴・シャワーの大変さ
- シャワーやお風呂の温度調節が難しい
- 「熱すぎる」「冷たすぎる」の幅が非常に広い
- 入浴自体を嫌がり、衛生管理に支障が出る
- 飲食の温度
- 熱い飲み物や冷たい食べ物に過敏な反応
- 「人肌」の温度でないと口にできない
痛覚
- わずかな刺激でも激しい痛みとして感じる
- 医療行為や注射時に通常以上の苦痛を感じる
- 衣服の縫い目やタグによる刺激が強い不快感や痛みとして認識される
- けがや傷の痛みが長く続く
- 痛みによる恐怖で医療機関受診を拒む

具体的な対処法
1️⃣温度調節の工夫
室温・衣服の管理:
- 室温を細かく調節し、子どもが感じる適温を見つける
- 重ね着しやすい服装を準備し、こまめに調節する
- 温度計を使って客観的な温度を確認する
- 季節の変わり目は特に注意して体温調節
入浴時の工夫:
- 温度を段階的に調節し、徐々に慣れる
- 入浴用温度計でお湯の温度を正確に測定
- 温度表示付きシャワーヘッドで適温を視覚的に確認
- 短時間から始めて徐々に入浴時間を延ばす
2️⃣痛み軽減の工夫
病院受診時の配慮:
- 事前に病院に特性を説明する
- どんなことをするかを事前に詳しく説明し、不安を軽減
- 好きな音楽や動画で気を紛らわせる
- 手を握るなどの安心できる配慮

3️⃣おすすめグッズ
| グッズ | 特徴 |
|---|---|
| デジタル温度計 | 室温・お湯の温度測定 |
| 冷却・温熱パッド | 首や脇などのクールダウン |
| サーモスタット付き暖房器具 | 設定温度で自動ON/OFF |
| 体温調節用ベスト | 簡単に温度調節可能 |
| 低刺激の絆創膏やテープ | はがす際の痛みや肌荒れの防止 |
医療機関との連携
事前準備と情報共有
医療機関に伝えるべき情報:
- 具体的な感覚過敏の内容(どのような痛みに特に弱いか)
- これまでの医療体験と反応の程度
- 効果的だった対処法
対処前の準備:
- 処置内容の事前説明(絵カードや写真を使用するとわかりやすい)
- 処置時間の見通しを具体的に伝える
- 安心グッズの持参(お気に入りのぬいぐるみなど)
- 家族が処置に付き添うことで安心感
歯科・小児科での配慮例
歯科治療時:
- 段階的な慣らし(まずは診察台に座るだけから)
- 使用する器具の事前説明。実際に触ってみる
- 短時間での処置と休憩の確保
予防接種・採血時:
- 最も細い針の使用を依頼
- 冷却パック等で痛みを軽減
- 麻酔テープ(事前に医師に相談)の使用を検討
- 好きな動画や音楽で注意をそらす

学校給食への対応
学校との連携ポイント
担任・栄養士との情報共有:
- 食べられる食品リストの提供
- 代替食品や栄養補助の相談
- 弁当持参の許可申請
- 食事時間の配慮(時間延長・場所の変更)
給食時の具体的な配慮例
- 少量からの提供
- 食材の分離提供
- 栄養補助食品の持参許可
- 弁当持参との併用

家庭でできる取り組み
食育
楽しい食体験の創造:
- 一緒に料理を作る体験で食材への興味を増やす
- 家庭菜園やベランダ栽培で食材への親近感を育てる
- 食べ物の絵本や図鑑で知識から入る
- 特別な日の食事で前向きな食体験
記録と振り返り
食事と成長の記録をつける:
- 食べた食品の記録
- 体調と気温と食欲の関係
- 成功した工夫や環境
- 体重・身長の成長曲線チェック
💝保護者の皆さんへ
無理せず長期的な視点で
味覚過敏・温痛覚過敏への対応では、「今すぐ」を求めず、お子さんのペースを大切にすることが最も重要です。
- 成長とともに徐々に改善することが多い
- 栄養バランスは長期的な視点で考える
- 専門機関、専門家と連携して取り組む
- 家族全体でサポートする体制づくり
感覚過敏は個性の一部です。正しい理解とサポートがあれば、お子さんらしい成長を支えることができます。

次回予告
第5回は「体内感覚の過敏さと家庭でできる工夫」について詳しくご紹介します。
- 空腹感や満腹感の調節が困難
- 心拍や呼吸の変化で不安になりやすい
- 疲労感や体調変化を敏感に感じる
このような体の内側からの感覚への対処法や、安心できる環境づくりの工夫をお伝えします。
【更新履歴】
2025年10月13日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
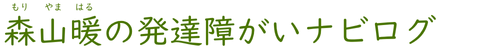







コメント