
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
第5回は、体内感覚過敏(内受容感覚過敏)について詳しく解説いたします。
「心臓の音が気になり眠れない」「疲れているのに休憩のタイミングが分からない」といったお子さんの悩みは、あまり知られていない感覚過敏かもしれません。
内受容感覚とは、主に心臓、呼吸、空腹感など「体の内部の状態」を察知する感覚です。これに加え、固有受容感覚(筋肉や関節の動き、体勢)の敏感さも、しばしば体の不安として現れることがあります。
正しい理解と家庭でできる工夫により、お子さんが自分の体と上手に付き合って、安心して過ごす環境を整えることができます。
❤️ 体内感覚過敏とは?
体内感覚(内受容感覚)について
体内感覚(内受容感覚)とは、私たちの体の内部の状態から送られてくる感覚情報のことです。これが敏感になると、必要以上に強く感じてしまいます。
- 心拍・呼吸:心臓の鼓動や呼吸のリズム(動悸、息苦しさなど)
- 消化器系:空腹感、満腹感、胃腸の動き
- 泌尿器系:膀胱の感覚、尿意
- 疲労感:体のエネルギーの消費、休息の必要性
💡 補足:他の感覚との関連
体温調節(暑さ寒さ)、平衡感覚等の敏感さも、しばしば体の不安として体内感覚過敏と同時に見られることがあります。
見られやすい症状
体内感覚過敏のあるお子様には、以下のような反応が見られることがあります
- 心拍と呼吸の変化に極度に敏感になる
- 胃腸の動きや内臓の感覚を強く意識してしまう
- 空腹感や満腹感の調節が困難
- 膀胱の感覚が敏感でトイレが頻繁にある
- めまいや平衡感覚の乱れを頻繁に感じる
情緒・行動面への影響
- 身体内部の変化に不安や恐怖を感じやすい
- 体調の細やかな変化で強いストレスを感じる
- 他人の感情や表情の変化にも過敏になる
日常生活での困難さ
- 食事量の調節ができない、過食や断食が多くなる
- 運動時の心拍数変化を恐れて身体活動を控える
- 疲労感が分からないので遊びすぎる、勉強しすぎる
- 学校で集中できなくなる
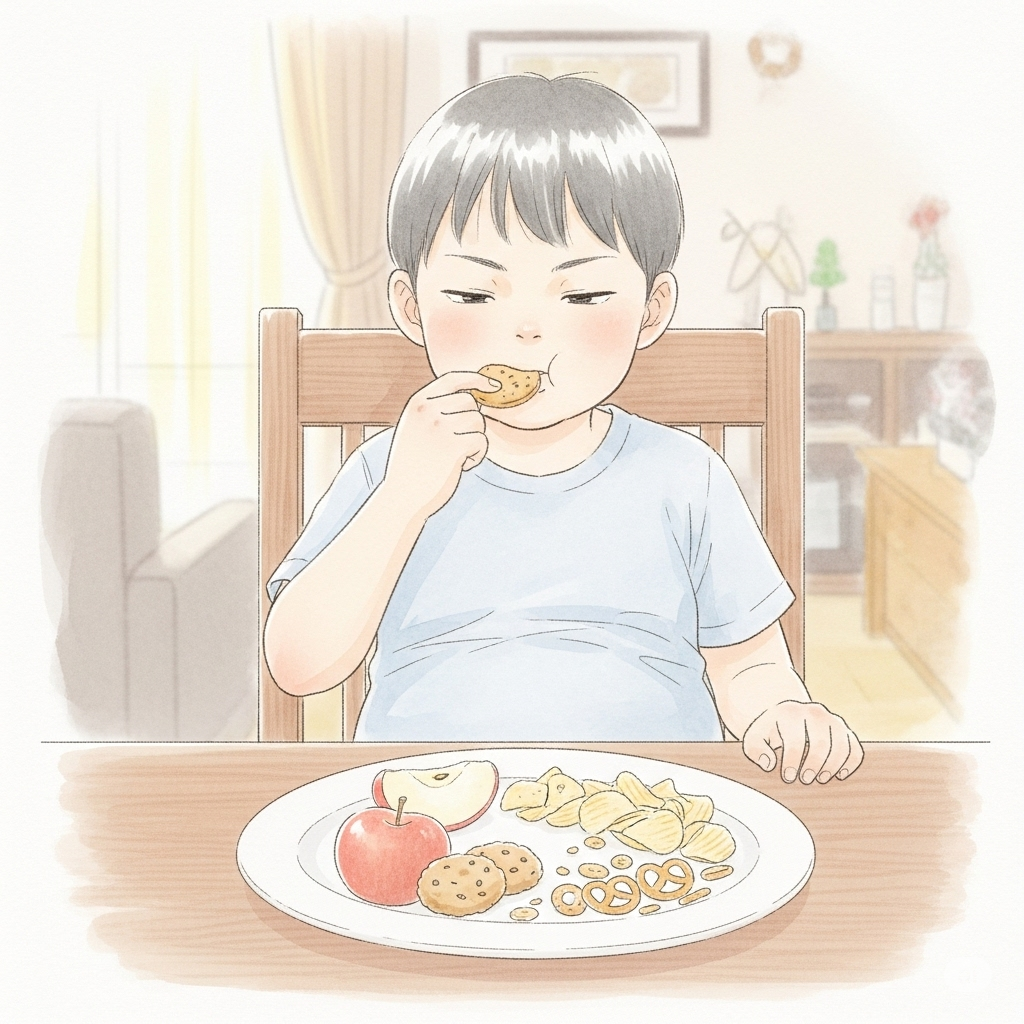
家庭でできる基本的な対処法
1️⃣ 身体感覚の理解と受容
お子さんに伝えたいこと:
- 身体の変化は正常な反応であることを説明する
- 「珍しいことではない」と伝えて安心させる
- 身体感覚を言語化できるよう支援する
- 不安を感じた時の対処法を一緒に考える
具体的な伝え方の例:
- ✅「心臓がドキドキするのは、体が一生懸命働いている証拠だよ」
- ✅「お腹がグルグルするのは、消化を頑張っているからね」
- ✅「疲れた時は体が『休憩して』って教えてくれてるんだよ」
2️⃣ 規則正しい生活リズムの確立
| 時間帯 | 具体的な工夫 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 朝 | 同じ時間に起床、朝日を眺める | 体内時計のリセット |
| 日中 | 適度な運動、規則的な食事 | 身体感覚の安定化 |
| 夕方 | 静的な活動、入浴でリラックス | 副交神経感の活性化 |
| 夜 | 同じ時間に就寝、暗い環境 | 質の良い睡眠の確保 |
食事のリズム作り
- 決めた時間に食事を摂る
- 空腹感・満腹感を意識させる声かけ
- 適量を視覚的に示す(お茶碗1杯など)
- 食事の間隔を一定に定める

3️⃣ 深呼吸とリラクゼーション法
4・4・8呼吸法
- 鼻から4秒で息を吸う(花の匂いを嗅ぐように)
- 4秒間息を止める
- 口から8秒でゆっくり息を吐く(ろうそくを消すように)
- これを5回繰り返す
腹式呼吸
- 手をお腹に置いて
- お腹が膨らむように鼻から息を吸う
- お腹がへこむように口から息を吐く
- ゆっくりとしたリズムで続ける
リラクゼーションの環境づくり
- 薄暗い照明や間接照明を使用する
- 静かな音楽やオルゴールを流す
- お気に入りのぬいぐるみ等を活用
- ラベンダーなど落ち着く香りを活用
おすすめグッズと感覚調整アイテム
身体感覚モニタリング用品
| グッズ | 特徴・効果 |
|---|---|
| パルスオキシメーター | 数値で安心感を得られる |
| スマートウォッチ | 日常的な体調管理 |
| 体温計 | 「熱っぽい気がする」 不安の解消 |
| 血圧計 | 高学年以上での自己管理 |
リラクゼーショングッズ
| グッズ | 特徴・効果 |
|---|---|
| 重みのあるブランケット | 深部圧刺激による安定感 |
| バランスボール | 前庭覚刺激と体幹強化 |
| ヨガマット・クッション | リラクゼーション時の快適性 |
| アロマディフューザー | 嗅覚を通じたリラックス効果 |
感覚調整アイテム
| グッズ | 用途 |
|---|---|
| 圧迫ベスト | 適度な圧刺激による安心感 |
| フィジェットトイ | 手先の感覚刺激でストレス軽減 |
| 感覚刺激ボール | 触覚を通じた身体感覚の調整 |
| センサーリーボトル | 視覚的なリラックス効果 |

学校生活での配慮と連携
内感覚過敏は目に見えにくいため、理解を得るのが難しい場合があります。主治医や心理士などに相談し、特性と学校で必要な配慮を記した情報提供書を提出することで、先生方の具体的な理解と支援が格段に進みやすくなります。
担任や養護教諭との情報共有
伝えるべき具体的な内容:
- どのような身体感覚に敏感か
- 症状が出やすい時間帯や状況
- 不安な時のサイン
- 効果的だった対処法
- 緊急時の連絡先
学校での具体的な配慮例
授業・学習面
- 集中が難しい時の休憩許可
- 座席の位置の配慮(廊下に近い場所など)
- 試験時間の延長や別室受験
- フィジェットトイの使用許可
体育・運動面
- 運動強度の調整
- 心拍変化への事前説明
- こまめな水分補給と休憩
- 体調確認の徹底
給食・休憩時間
- 食事量の個別対応
- トイレ利用自由
- 静かな場所での休憩許可
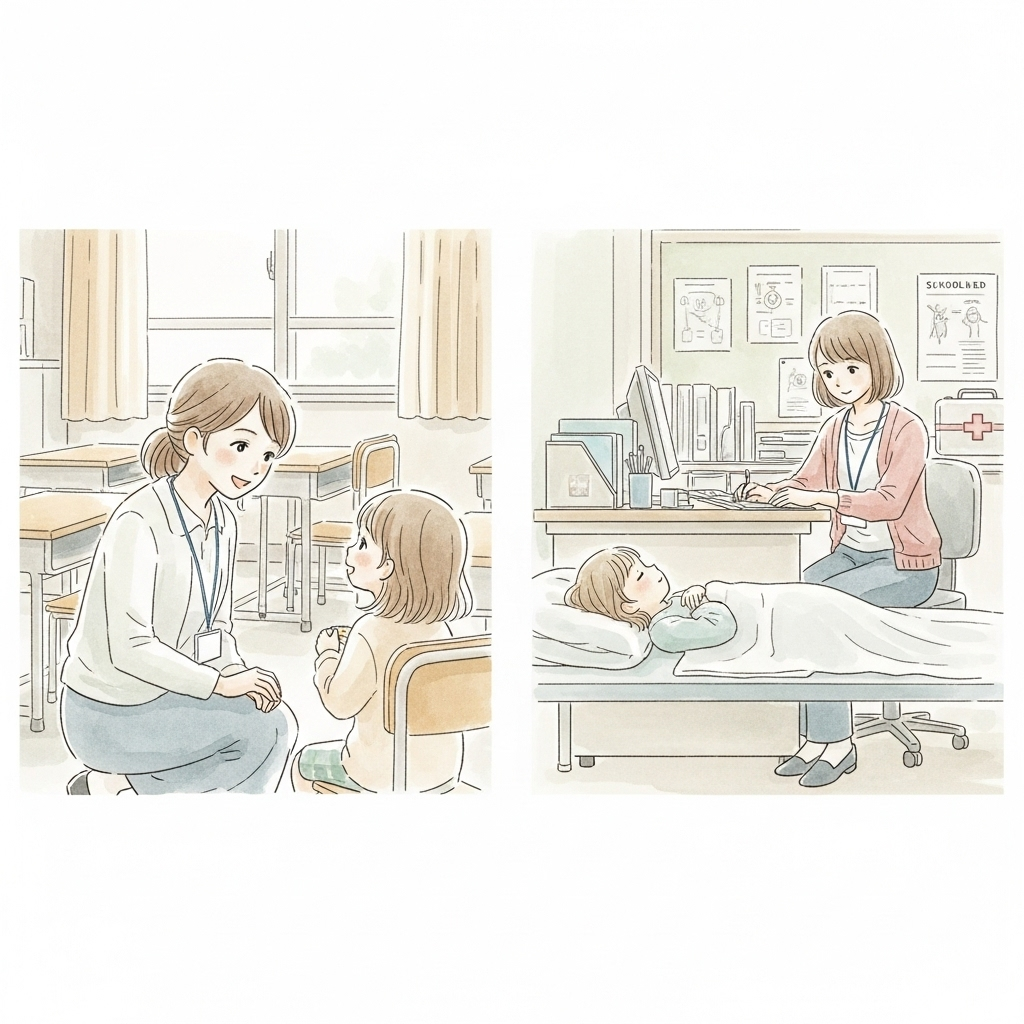
家庭でできる感覚訓練
心拍感知訓練
- 静かな環境で座る
- 手首に指を当てて脈拍を感じる
- 数を数えながら15秒間測定
- 4倍にして1分間の心拍数を計算
- 実際の測定値と比較する
空腹・満腹感覚訓練
- 食事前に安心度を10段階で評価
- 食事中に満腹度をチェック
- 「お腹6分目」で一度止まる
- まだ食べたいか確認する
- 適切な量をよそう
家族ができるサポート
日常的な声かけ
- ✅「体の声を聞いてみよう」
- ✅「今、どんな感じ?」
- ✅「一緒に深呼吸してみよう」
- ✅「大丈夫、体は普通に働いているよ」
環境づくり
- 家庭内のストレスを軽減
- テレビ番組の音量は控えめに
- 就寝前のデジタル機器の使用を控える
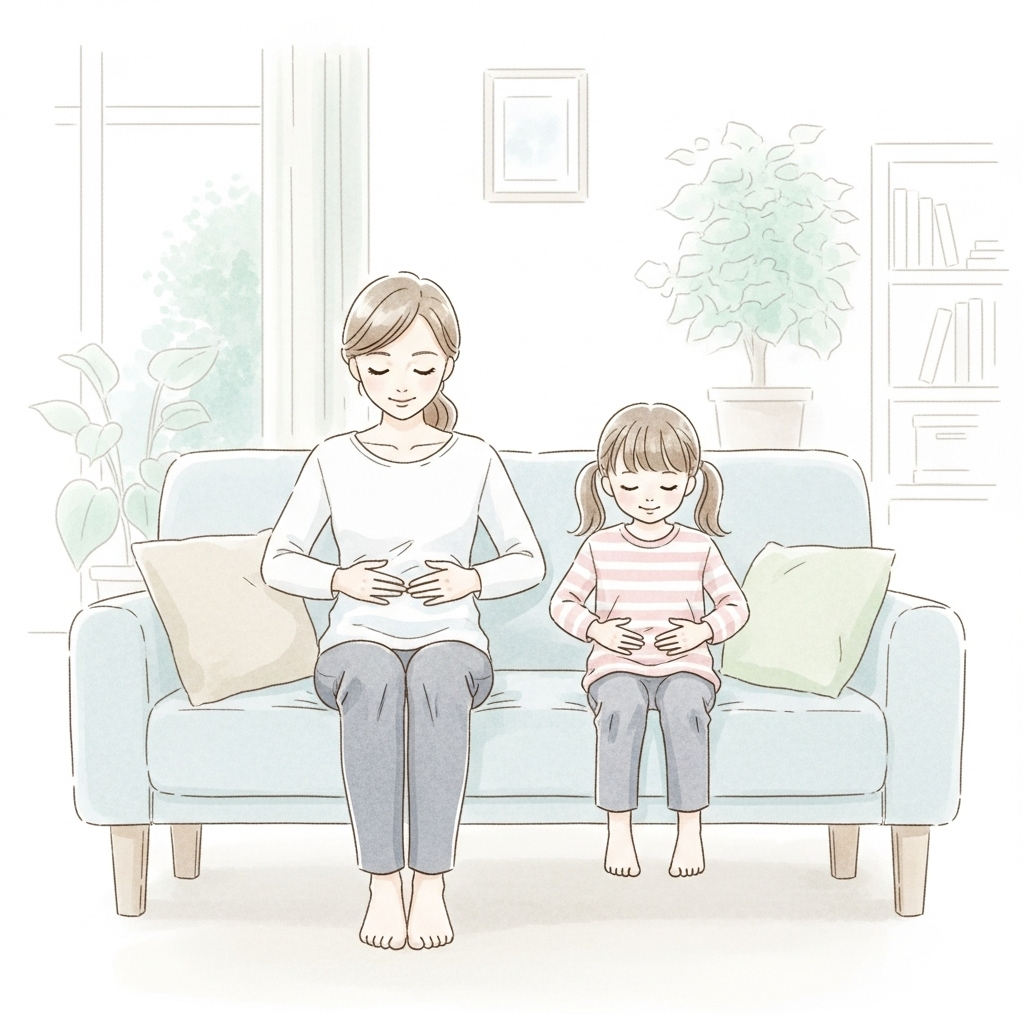
成長と自立に向けて
セルフモニタリング能力を育てるため、年齢に応じた自己管理を促します。
幼児期(3~6歳)
- 気持ちを表情カードで表現
- 体調を色で表現(赤=疲れた、青=元気など)
- 簡単な体調記録(シールを貼るなど)
小学校低学年(6~9歳)
- 1日2回の体調チェック(朝・夜)
- 10段階評価で疲労度や気分を記録
- 自分なりの対処法を見つける
小学校高学年以上(10歳以上)
- スマートウォッチ等で客観的なデータ収集
- 詳細な体調日記の記録
- 自分から周囲に説明できるスキル習得
自立への準備
自立に向けて身につけたいスキル:
- 自分の特性を客観的に、客観的に説明できる
- 効果的な対処法を複数持つ
- 周囲にサポートを正しく求められる
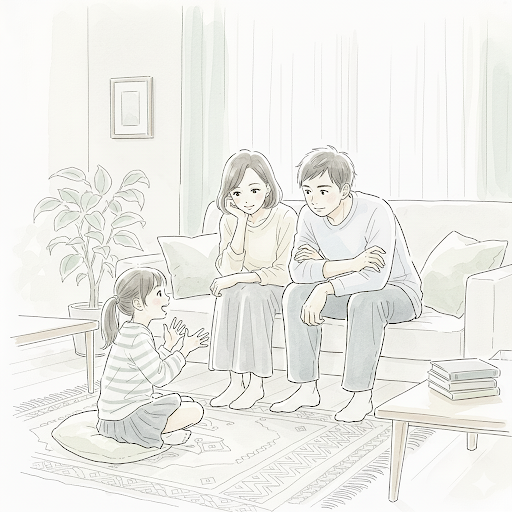
🌱保護者の皆さんへ
体内感覚過敏は、目に見えにくいため、周囲の理解が得られにくい場合があります。
⭐重要!
- お子さんの感じ方を信じること
- 長期的な視点で成長を見守ること
- 専門機関との連携を積極的に行うこと
- 家族全体でサポートする体制づくり
成功体験の積み重ね
小さな成功を積み重ねることで、お子さんの自信と自己肯定感が向上します
- 深呼吸で落ち着けたことを褒める
- 体調を正しく伝えられたことを評価する
- 不安な時に自分なりの対処法を使えたことを褒める
- 困った時に助けを求められたことを称賛する
体内感覚過敏のあるお子さんは、自分の体と向き合う力が人一倍必要です。適切なサポートがあれば、それは将来の大きな強みとなるはずです。

次回予告
第6回は「感覚鈍麻(感覚の鈍さ)」について詳しく解説します。痛みや温度の変化、空腹や疲労への気づきが弱いことで日常生活にどんな困りごとが生じるのか、安全面のリスクや家庭・学校でできるサポート方法についてもご紹介します。
【更新履歴】
2025年10月13日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
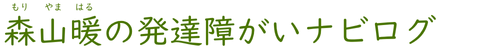







コメント