
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
これまで感覚過敏について詳しく解説してきましたが、感覚の特性には「感じすぎる」だけでなく「感じにくい」という特性もあります。
感覚鈍麻(感覚低反応性)は、刺激に対する反応が弱く、周囲からは「我慢強い子」「気づかない子」に見えることがあります。しかし、この特性はけがや事故、体調不良の発見の遅れなど、安全・健康面で大きなリスクを伴います。
🧠感覚鈍麻とは?
基本的な理解
感覚鈍麻(感覚低反応性)とは、脳の感覚処理において、通常なら感じるべき刺激を感じにくい状態です。
- 普通の人は「5」で感じる刺激を、「8」や「10」でやっと感じられる
- 軽い刺激では脳が信号を感じない
- 強い刺激でも反応できない
感覚過敏との違い

| 感覚過敏 | 感覚鈍麻 | |
|---|---|---|
| お子さんの反応 | 刺激に過剰に反応する | 刺激に気付かない・ゆっくり |
| お子さんの行動 | 刺激を避ける | 刺激に反応しない |
| 周囲の気づき | 比較的簡単に分かる | 分かりにくい |
| リスク | 不安・パニック | 安全面、健康面の危険 |
👂聴覚鈍麻:音への反応が鈍い

見られやすい症状
- 名前を呼んでも振り返らない
- 何度も声をかけないといけない
- 大きな音でも驚かない
- 危険を知らせる音に反応しない
具体的な対処法
- 肩をたたいて注意を向けてから話す
- 視線を合わせて話しかける
- ジェスチャーを活用する
- 視覚的な合図(ライトの点灯など)を使う
おすすめグッズ
| グッズ | 用途・工夫のポイント | 特徴 |
|---|---|---|
| 振動するアラーム | 床起・予定のお知らせ | 聞こえなくても手元で気付ける |
| 光で知らせるドアベル | 来客・インターホン通知 | 音を光で視覚的に知らせる |
| 振動機能スマート付きウォッチ | 予定・メッセージ・タイマーの通知 | 手首の振動で気づきやすい |
🤲 触覚・温痛覚鈍麻:温度や痛みに気づきにくい
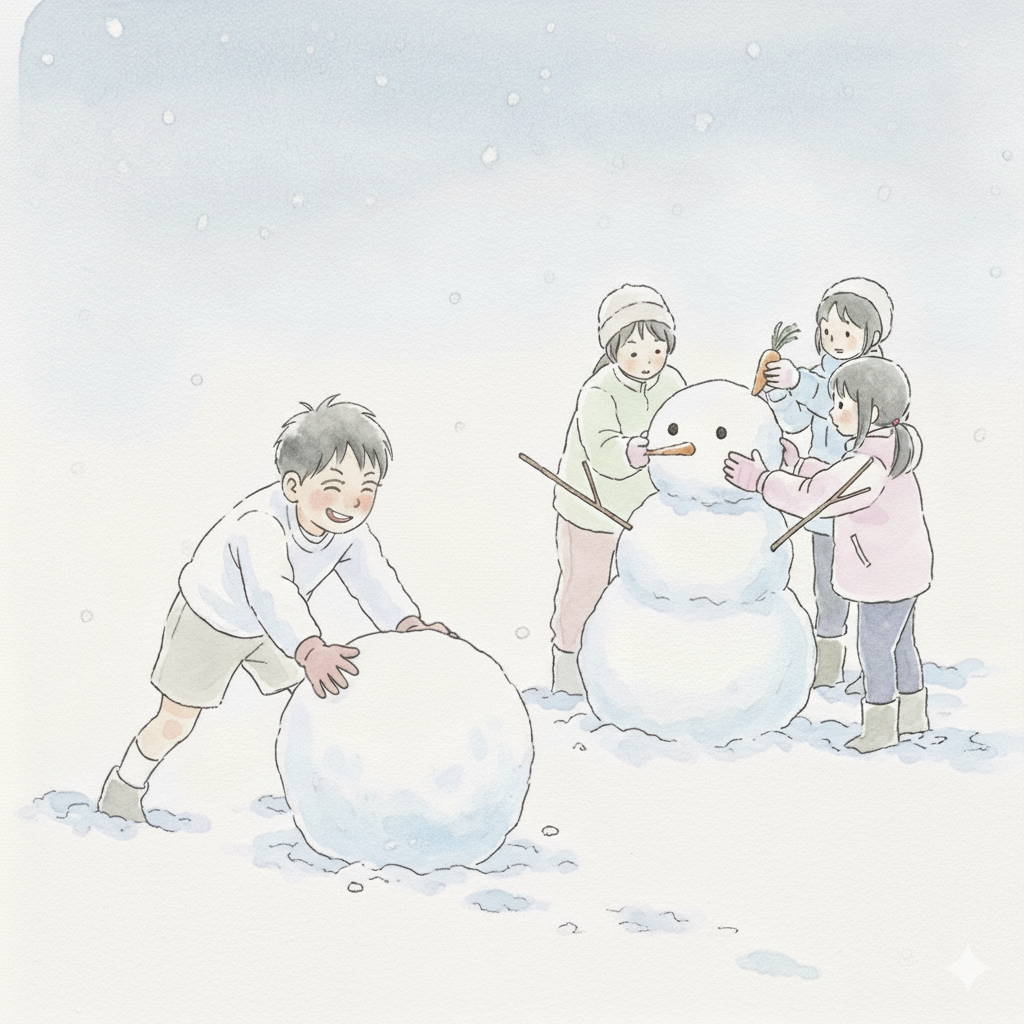
見られやすい症状
温度感覚の問題:
- 暑さ・寒さを感じにくい
- 真夏でも厚着、真冬でも薄着
- 熱中症や風邪のリスク
痛みが分からない:
- 転んで血が出ていても分からない
- 熱さに気づかずいつの間にか火傷
- 虫歯が進んでも痛みを感じない
具体的な対処法
温度管理のサポート
- 温度計で客観的に確認
- 季節に応じた服装の準備
- 定期的な水分補給の声かけ
- 室温管理を大人が行う
安全管理の徹底
- 毎日の身体チェック(入浴時など)
- 定期的な健康診断
- かかりつけ医との連携
- 体調の記録
おすすめグッズ
| グッズ名 | 用途・工夫点 | 特徴・選び方例 |
|---|---|---|
| 体温計/温度計 | 客観的な温度・体調の確認 | 毎日の健康・安全管理に必須 |
| マッサージブラシ | 適度な皮膚刺激による感覚体験 | 毎朝・入浴時のケアにも |
| 重みのあるブランケット | 深部圧刺激で安心感・リラックス | 就寝時やリラックスしたい時 |
👃👅 嗅覚・味覚鈍麻:匂いや味がわからない
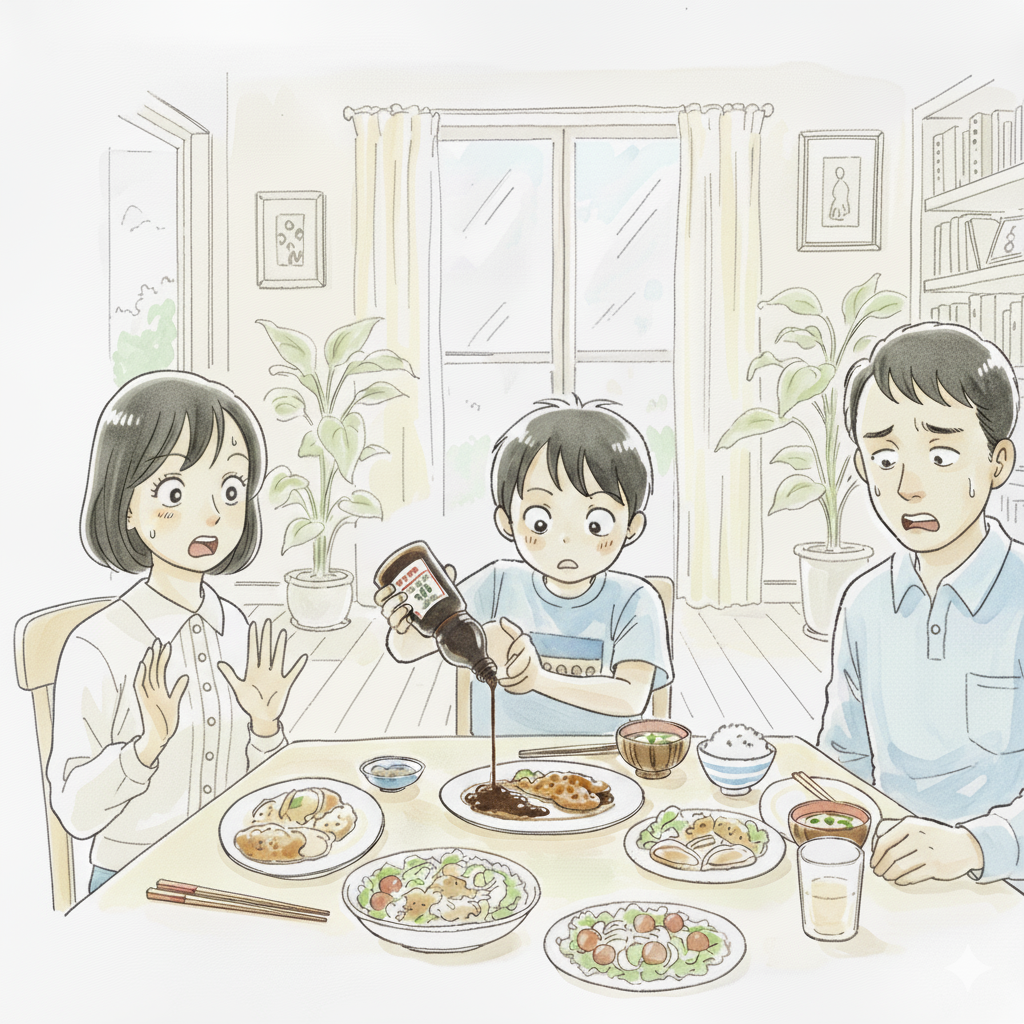
見られやすい症状
- 食べ物の危険性に気付きにくい(傷んだ食べ物を食べてしまう)
- 煙やガスの匂いに気付きにくい
- 味の濃いものばかりを好む
具体的な対処法
- 消費期限を記載したラベルを張る、お知らせアプリを使う
- 煙感知器・ガス警報器の設置
- 香辛料やだしを多めにして風味を付ける
おすすめグッズ
| グッズ名 | 用途・工夫点 | 特徴・選び方例 |
|---|---|---|
| ガス警報器 | ガス漏れ・火事の早期発見 | 視覚と音で安全管理 |
| 香辛料・だし | 味や風味の調整 | 刺激不足時にアクセント |
| デジタル塩分計 | 塩分の可視化 | 塩分の取り過ぎを予防 |
🧠 体内感覚鈍麻(内受容感覚鈍麻):疲労や空腹、尿意がわからない
見られやすい症状
- 食事のタイミングをつかめず空腹でも食事をしない
- トイレに行きそびれて失敗する、おむつが濡れても気付かない
- 疲れているのに休憩をとらない
具体的な対処法
- 決まった時間に食事をとる
- 食事量を視覚的に示す(お茶碗1杯など)
- 水分や食事摂取量・トイレ回数を家庭や園で記録
- あらかじめ休憩を予定に入れる
- アラームやタイマー、目で見てわかるスケジュール表を使う
おすすめグッズ
| グッズ名 | 用途・工夫点 | 特徴・選び方例 |
|---|---|---|
| 食事量管理プレート | 食事量や食材の見える化 | プレート仕切り・量が一目で分かる |
| 生活習慣管理アプリ | 食事時間、休憩時間の管理 | アラームで適切な時間をお知らせ |
| バイタルサイン記録ノート・アプリ | 日々の体調変化やモニタリング結果を記録 | テンプレート付きノート/家族共有アプリで複数人利用可能 |
学校・園における対応
学校へ伝えたい情報
- どの感覚(痛み・温度・聴覚・トイレ・けがなど)が鈍いのか
- 日常で配慮が必要な行動(例:転んでも保健室に行かない、食事量が多い/少ない、トイレは声かけが必要など)
- 家庭での観察記録(体調や失敗の状況、気づかないこと・気づきにくい場面)
- 効果的だった家庭での対処法(声かけのタイミング、モニタリング方法など)
学校側での配慮例
| 項目 | 配慮や支援の例 |
|---|---|
| 健康・体調管理 | 毎朝のシート記入・顔色チェック・健康観察 |
| けが・事故防止 | 体育や休み時間の見守り/転倒時は自己申告を待たず確認 |
| 食事・給食 | 食事量の見守り・食べ残し/食べ過ぎの状態を確認 |
| 排泄・トイレ | トイレ表の作成/定時の声かけ、失敗時も穏やかな対応 |
| 服装・体温調節 | 季節・気温に合った服装の声かけ/調節の手伝い |
| 疲労や体調変化 | 「疲れた」「気持ち悪い」等本人からの訴えを待つのではなく、担任や養護教諭から積極的に声をかける |

個別指導計画や支援会議での情報共有
- 「学校保健管理シート」などで特性と対応を明確化、関係者で共有
- 支援会議や学期ごとの面談時に、配慮した内容の見直し
- 家庭と学校が連絡ノートやICTで日々の記録や気づきを相互共有(写真や数値、記録アプリも活用するとより効果的)
感覚の自己理解と自己表現のサポート
- 本人が意思表示しやすい伝達方法(担任にヘルプカードを渡す、言葉で言わなくても手を挙げれば退室できる等)を一緒に考える。
- 支援のタイミングや状況を一緒に考える(「どんな時に困る?」「どんな助け方が嬉しい?」等)。
- 給食や体育、休憩などの連絡カードや自己申告表を導入
💝保護者の皆さんへ
感覚鈍麻は「鈍感」ではなく「感覚の特性」として理解することが大切です。
- お子さんの感覚を理解すること
- お子さんの様子を周囲が観察し、サポートする
- 安全と自立のバランスを考える
- お子さんの得意な感覚も生かす
感覚鈍麻のあるお子さんも、正しい理解とサポートがあれば、安全で豊かな生活ができます。

まとめ
本シリーズでは、感覚過敏と感覚鈍麻について、全6回を通じて子どもたちのさまざまな「感じ方」に寄り添うヒントをお届けしました。
それぞれの感覚特性は「わがまま」や「努力不足」ではなく、その子自身の大切な個性です。今回の内容が、ご家庭や学校、支援の場で具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
今後も子どもたち一人ひとりの声をしっかり受け止め、安心して成長できる環境づくりを続けていきましょう。
このシリーズが、皆さまの理解と実践を支える一助となることを心より願っています。
【更新履歴】
2025年10月13日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
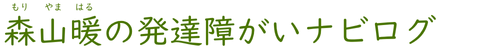







コメント