
著者:森山 暖(もりやま はる)
公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)
プロフィールページへのリンク
第2回で「行動で書く」スキルを身につけ、「いいところ」のハードルを下げる実践をされましたね。現状把握表(ポジティブ項目リスト)は随分と充実したことと思います。
第3回は、その増えた項目を生活場面や性質によって「分類・整理」し、全体像を「見える化」していきます。この「カテゴリー分け」によって、お子さんと自分の生活パターンや得意・苦手分野が驚くほどクリアに見えてきます。
第3回で体験すること
🎯 第3回の目的
行動をグループ分けして、生活のパターンや傾向を把握し、「この分野は得意」「この分野で困りがち」といった全体像を掴みます。
⏰ 第3回の流れ(約90分)
- 前回の宿題振り返り(25分)
- カテゴリー分けとは?(15分)
- 自分編のカテゴリー分けワーク(20分)
- 子ども編のカテゴリー分けワーク(20分)
- 発見の共有と次回への宿題(10分)
前回の宿題振り返り~「子どもをほめた」実践報告
第3回では、前回の宿題「子どもを具体的にほめる」実践の体験談から始まります。さらに、「身近な大人をほめた」宿題の成果も共有され、「ほめる」ことの効果を参加者全員で実感します。多くの参加者が「行動で」ほめることの効果を実感した報告をしてくれます。
✨ 参加者の実践体験談
Jさん(6歳女児の母)の体験
「いつもは『優しいね』と言っていましたが、『お友達が泣いているときに声をかけてくれたね、優しいね』と具体的に言ってみました。娘は『ママ、見てたの?』ととても嬉しそうでした」
Kさん(8歳男児の母)の体験
「『宿題に10分間集中できたね』と言ったら、息子が『今度は15分やってみる!』と言ってくれました。具体的にほめると、子どもも何を頑張ればいいかが分かるんですね」
🔍 「行動で」ほめることの効果
子どもへの効果
- 自信の向上:「何ができているか」が明確になる
- 継続意欲:「もっと頑張ろう」という気持ちが生まれる
- 自己理解:自分の良いところを客観視できる
保護者への効果
- 観察力の向上:子どもの行動をよく見るようになる
- 関係性の改善:親子のコミュニケーションが増える
- ポジティブな循環:ほめることで自分も嬉しくなる

カテゴリー分けとは?~生活を「見える化」する技術
📊 なぜカテゴリー分けをするのか?
第2回で増やした行動項目を、そのままリスト状態にしていては全体像が見えません。カテゴリー分けによって
- 得意分野・苦手分野が一目で分かる
- 生活のバランスを客観視できる
- 改善の優先順位を決めやすくなる
- 成長の方向性が見えてくる
🗂️ カテゴリー分けの方法
参加者は、色分けされたカードや付箋(ポストイット)を使い、現状把握表の行動項目を「環境(生活場面)」や「機能(行動の性質)」によって分類していきます。
📋 カテゴリー分けの手順
- 項目を付箋やカードに書き写す(5分)
- 似たような場面・性質のものをグループにする(10分)
- 各グループにカテゴリー名をつける(5分)
- ペアで見せ合い、新しい視点や気づきを共有する(10分)

自分編のカテゴリー分けワーク
👩 保護者の生活カテゴリー例
保護者の行動は、主に以下のようなカテゴリーに分類されることが多いです
| カテゴリー | 行動例(いいところ・努力しているところ) | 行動例(困ったところ) |
|---|---|---|
| 🏠 家事・生活管理 | ・毎日料理を作る ・洗濯物を畳む ・部屋をきれいに保つ | ・家事が思うように進まない ・片付けが苦手 ・時間管理がうまくいかない |
| 💪 健康・セルフケア | ・規則正しい生活をする ・バランスの良い食事をとる ・適度に運動する | ・夜更かしが続く ・食事が偏りがち ・運動不足 |
| 🤝 人付き合い・社会性 | ・ご近所に挨拶する ・友人に相談する ・支援を求める | ・人との関わりが苦手 ・一人で抱え込みがち ・相談するのが難しい |
| 👶 育児・子どもとの関わり | ・子どもの話を聞く ・一緒に遊ぶ ・宿題を見る | ・つい怒鳴ってしまう ・子どもとの時間が少ない ・関わり方が分からない |
| 😌 気持ち・ストレス対処 | ・音楽を聴いてリラックス ・深呼吸をする ・一人の時間を作る | ・イライラしやすい ・ストレスが溜まりやすい ・気持ちの切り替えが苦手 |
💡 自分編カテゴリー分けの発見例
Lさん(7歳男児の母)の発見
「『育児・子どもとの関わり』のカテゴリーが他より少なくて、『家事・生活管理』ばかりに意識が向いていることに気づきました。子どもともっと関わる時間を意識的に作りたいと思います」
子ども編のカテゴリー分けワーク
👶 子どもの生活カテゴリー例
子どもの行動は、発達段階に応じて以下のようなカテゴリーに分類されます
| カテゴリー | 行動例(いいところ・努力しているところ) | 行動例(困ったところ) |
|---|---|---|
| 😴 睡眠・生活リズム | ・決まった時間に寝る ・朝一人で起きる ・昼寝をきちんとする | ・なかなか寝つけない ・朝起きるのが苦手 ・生活リズムが不規則 |
| 🍽️ 食事・食習慣 | ・好き嫌いなく食べる ・箸を正しく使う ・食後片付けを手伝う | ・偏食が多い ・食事に時間がかかる ・食べこぼしが多い |
| 👕 着脱・身支度 | ・一人で服を着る ・靴を正しく履く ・身支度を整える | ・着替えに時間がかかる ・服の前後が分からない ・靴を間違えて履く |
| 📚 学習・探求・知的活動 | ・宿題に取り組む ・本を読む/調べ物をする ・好きなことに没頭する | ・宿題をやりたがらない ・集中が続かない ・興味のないことは拒否する |
| 👫 対人・社会性 | ・友達と仲良く遊ぶ ・挨拶をする ・順番を待つ | ・友達との関わりが苦手 ・集団行動が難しい ・ルールを守れない |
| 💚 気持ちの調節 | ・怒りを抑える ・我慢する ・悲しい時に表現できる | ・癇癪を起こしやすい ・感情の切り替えが苦手 ・泣き止むのに時間がかかる |
🌟 子ども編カテゴリー分けの重要な発見
よくある発見パターン
- 「対人・社会性」が苦手だと思っていたけれど、「家族とは上手にコミュニケーションできている」
- 「学習」は困りがちだけど、「生活習慣」はとてもよくできている
- 「気持ちの調節」は難しいけれど、「身支度」は自立している
Mさん(5歳女児の母)の驚きの発見
「娘は『対人・社会性』のカテゴリーが苦手だと思っていましたが、実際に分類してみると『年下の子には優しい』『家族には甘える』『好きな友達とは遊べる』など、できていることもたくさんありました。全部が苦手なわけじゃないんですね」
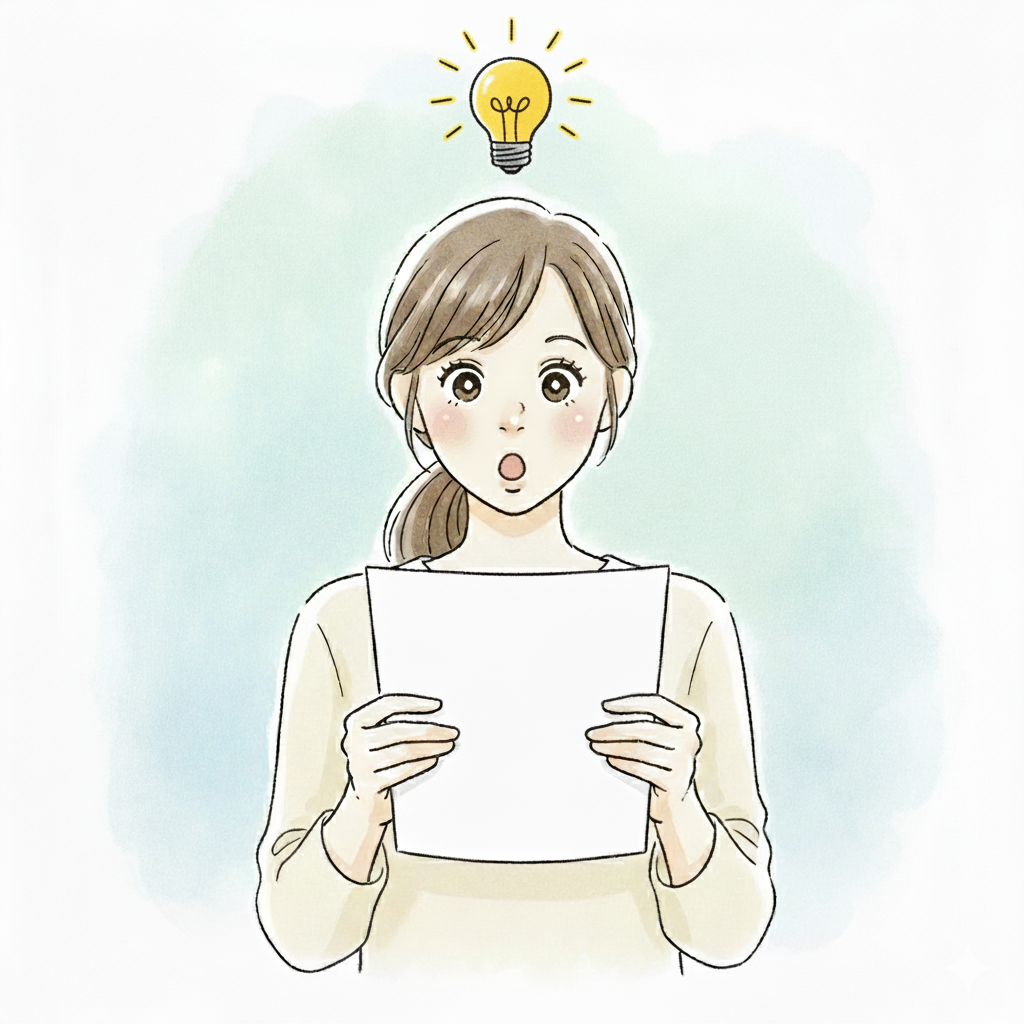
カテゴリー分けから見える全体像
📈 バランスの可視化
カテゴリー分けが完成すると、生活全体のバランスが一目で分かるようになります。
🔍 発見できること
- 得意分野:「いいところ」が多いカテゴリー
- 成長分野:「努力しているところ」が多いカテゴリー
- 困り分野:「困ったところ」が多いカテゴリー
- 見落としていた分野:項目が少なすぎるカテゴリー
💡 カテゴリー分析のメリット
| 発見 | 活用方法 |
|---|---|
| 得意分野が明確 | 自信を持って伸ばし続ける、他の分野にも応用する |
| 苦手分野が具体的 | 優先順位をつけて、一つずつ取り組む |
| 意外な得意分野 | 新しい可能性として伸ばしていく |
| 見落としていた分野 | 観察を増やし、新しい発見を探す |
🎯 具体的な活用例
Nさん(6歳男児の母)の活用法
「息子は『学習』のカテゴリーで困ることが多いですが、『対人・社会性』がとても得意だと分かりました。お友達と一緒に勉強する時間を作ったり、グループ学習を取り入れることで、得意分野を活かして苦手分野をサポートできそうです」

ペアでの共有タイム~新しい視点の発見
🤝 お互いの発見を共有する
カテゴリー分けが完了すると、参加者同士で結果を見せ合い、感想や気づきを共有します。
共有タイムでよく出る感想
- 「うちの子、こんなに得意分野があったんですね」
- 「同じカテゴリーでも、子どもによって全然違うんですね」
- 「自分も意外にできていることが多かった」
- 「優先順位が見えてきて、気持ちが楽になりました」
💬 ペア共有の効果
- 多様性の理解:同じ年齢でも一人ひとり違うことを実感
- 新しいアイデア:他の家庭の工夫や視点を学ぶ
- 安心感:「うちだけじゃない」という仲間意識
- 客観視:他の人から見た自分・子どもの良いところ

第3回の宿題~観察力をさらに深める
📚 3つの宿題
宿題1:カテゴリー別観察強化
- 得意分野をさらに観察:どんな時に、どんな風にできているか詳しく記録
- 見落としていた分野に注目:項目が少なかったカテゴリーで新しい発見を探す
- 現状把握表をカテゴリー別に整理:分類した状態で見やすく整理
宿題2:子どもをほめる実践(カテゴリー版)
- 得意分野を積極的にほめる:子どもの自信を育てる
- 困り分野でも「努力」や「小さな成功」を見つけてほめる
- カテゴリー別にほめた内容を記録:バランスよくほめているかチェック
💡 カテゴリー別ほめ方例
- 対人・社会性:「お友達に優しく声をかけたね」
- 学習:「宿題を5分間頑張ったね」
- 生活習慣:「一人で歯磨きできたね」
宿題3:家族と情報共有
- 可能なら夫や家族にカテゴリー分析結果を見せる
- 子どもの得意分野について話し合う
- 家族みんなで子どもの良いところを見つける意識を共有
🤔 宿題でつまずきやすいポイントと対策
Q: 見落としていた分野で新しい発見ができない時は?
A: まずは「その分野を意識して見る」ことから。例えば「気持ちの調節」なら、子どもが感情を表現している場面を意識的に観察してみましょう。
Q: 困り分野ばかりに目が向いてしまう時は?
A: 「1日1回は得意分野を見る」という目標を決めてみてください。得意分野から見ることで、心に余裕が生まれます。

第3回を終えて~全体像が見えた喜び
🗺️ 「地図」を手に入れた感覚
第3回を終えた参加者の多くが感じるのは、「子育ての地図を手に入れた」ような感覚です。
🗺️ カテゴリー分析で得られる「地図」
- 現在地:今、どの分野でどんな状況にいるか
- 目指す方向:どの分野を伸ばし、どこを改善すべきか
- ルート:得意分野を活かした成長のアプローチ
- 安心材料:できている分野がこんなにたくさんある
🌱 参加者の変化
Oさん(7歳男児の母)の感想
「息子のことを『問題の多い子』だと思っていましたが、カテゴリー分けをしてみると『対人・社会性』『生活習慣』はとても優秀で、困るのは主に『学習』『気持ちの調節』の2分野だけでした。困っているのは全体の3分の1程度なんですね。こんなに得意分野があるなら、もっと自信を持って子育てできそうです」
🔮 次回(第4回)への期待
次回は「ギリギリセーフ!をみつける!」をテーマに、困った行動の裏にある「実は頑張っているところ」を発見し、見方を変える革新的な視点を手に入れます。
🎯 次回予告:第4回のポイント
- 「ギリギリセーフ」という革新的な視点との出会い
- 困った行動を「頑張り」に変換する技術
- ペアワークでお互いの「ギリギリセーフ」発見
- 子どもの困り行動への新しいアプローチ法
参加者へのエール
今日から、お子さんと自分自身を見る「解像度」が格段に上がります。
カテゴリー分析によって見えてきた得意分野を大切に育て、困り分野は焦らず一つずつ取り組んでいけば、きっと子育てがもっと楽しくなるはずです。
完璧を目指さず、今できていることを大切にしながら、家族みんなで成長していきましょう。
次回「第4回 ギリギリセーフ!をみつける!」でお会いしましょう 🌸

【参考・引用】
NPO法人アスペ・エルデの会『楽しい子育てのためのペアレント・プログラムマニュアル』、2014年
【更新履歴】
2025年10月16日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。
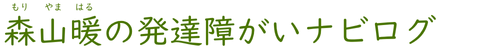









コメント